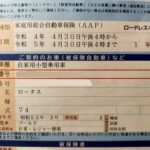どうもサイレンサー内部の燃え残りが路面に垂れている様子です。
こんなのどうすりゃいいんだよ。
ペットボトルで受けでも作ろうか?
とまあ悩んだ挙句の話です。
当記事の目次
KDX125SRの純正サイレンサーには謎のチューブが付いている

コレは何だって話です。
KDX125SRの純正サイレンサーからは謎のホースが生えています。
サイレンサーからガソリンホースが生えていると思えばよろしい。
片側は大気開放になっています。
当倶楽部にはKDX125SRは2台あります。
もう長い付き合いになる1号機には最初からR.S.Vのサイレンサーが入ってたので純正サイレンサーは2号機が初めてなのですよ。
いろんなバイクに乗ってきたワタクシですがこんなのは初めてです。
サイレンサーから生えるホースが何に使われるのか全く想像ができませんでした。
当倶楽部のレストア中のKDX125SR2号機は普通に駐車してるだけで路面に黒いシミができるのですよ。
その原因はどうやらこのホースからポタポタと排出されてる黒い液体らしいことが判明しました。

オイル染み。

汚れたバイクカバー。
これくらい勝手に汚れる。
ホースにボルト突っ込んで暫定的に止めてはいる。
この液体、素晴らしく汚い。
粘度があってベトつくし、白い樹脂パーツを黒くまだらに染めてしまうくらいの破壊力があります。
※ほとんどのKDX125SRのリアブレーキガードの白い樹脂は黒い点で汚れてるのが普通です。これ全然落ちません。
これはいただけない。
暫定的に地面に段ボールを敷いて防ぐことはできますが、
コンクリートに付いた黒いシミが拡大する前に根本的に何とかしなくてはいけません。
ちなみに・・
ちょっと昔のバイクのサイレンサーは非分解式なものが多いです。
※今もそうかもしれないけど。
バイクのサイレンサーを違法改造して騒音をまき散らす馬鹿が佃煮にするほどいたから、
行政指導が入ってそういう作りにしたという噂が昔からありますな。
※お金持ちの馬鹿どもは最初から純正マフラーなんか使わずに社外マフラーにしちゃうし、
お金のない馬鹿どもは最初に純正サイレンサーをぶった切っちゃうので全く意味がないのですが。
その弊害として、
「サイレンサーの消音材が劣化したら、マフラー丸ごと交換。」
というまことにエコではない出費を強いられる選択を強いられることになるのです。
※純正マフラーって複雑な形状で保管しずらいし、廃棄もしずらいんですがねえ。
特にエンジンをぶん回せないライダーが乗った2stのサイレンサーは詰まり気味のものが多いです。
※2stは4stに比べてキャブの中をガソリンがザブザブ流れるイメージで低回転では濃い目になりがちです。
2stオイルと混合されたガソリンを完全に燃やすように高回転を使って走ればいいのですが、
エンジンを回せない初心者やエンジンを回せない街中で使われた個体はチャンバー内に燃え残った2stオイルがたくさん残ることになるのです。
※特に古い2stは焼き付き防止でオイル濃度が濃い目になってることが多いです。
公道で使う2stの場合、どうやっても高回転をキープしずらいです。
※免許の点数を気にしなければいけるんですがね。
そんな時は すんごい迷惑ですが 高速道路で1区間だけでもエンジンをぶん回して乗るとだいぶマシになります。
そんなことをしてる初心者はなかなかいませんしねえ。
ゆえに。
2stバイクは純正でサイレンサーがチャンバー部と別体式になってるものが多い。
サイレンサーだけ、交換出来たりするのですな。
社外品のサイレンサーは分解して内部の清掃が出来たりしますな。
チャンバーごと変えちゃうと金属音が煩いんだけど、
サイレンサーだけを社外品にしても純正並みに静かなものが多いし。
※でも中古でもメチャメチャ高いよね。2stの社外サイレンサー。
大昔のRZ250や初期のRZ250R(おむすびテール)は葉巻型のサイレンサー一体型チャンバーでした。
このチャンバーは内部のサイレンサーを引き抜いて消音材を交換出来ましたな。
※サイレンサーを抜くためのボルトがオイルだらけで触るのもためらうくらいなのが普通でしたが(笑)
後期のRZ250Rのチャンバーはマイナーチェンジでサイレンサーが別体になりました。
※見た目はレーサーっぽいのですがイマイチ抜けが悪くてワタクシは嫌いでした。
ホースは燃え残った混合ガスを排出するためのもの

純正サイレンサーを装着したKDX125SRのエンジンを始動すると、
サイレンサーの排気口だけでなく、このホースからも白煙を吐きます(笑)
走行中であろうがアイドリング時であろうが容赦なくサイレンサー内に溜まった燃え残った2stオイル混合ガスを排出し続けます。
路面に(笑)
※環境性能は0点ですな。
ああそうか。
このホースははサイレンサーの中に燃え残った混合気を排出するためのものみたいですな。
※位置的に一番液体が集まりそうな箇所に生えているし。
2stのサイレンサーは燃えカスで詰まることが多いのです。
サイレンサーが燃えカスで詰まり気味の2stバイクでエンジンをぶん回すとサイレンサーから盛大に黒い液体をぶちまけますな。
高速に乗ると白煙で煙幕状態になるのはもちろん、後続車両に黒いオイルがバンバンとびかかるのです。
※後方廃棄のTZR250はこの点でマスツーリング時にはとんでもなく嫌われ、隊列の最後尾になることが多かったのです。
KDX125SRは燃えカスを車体下方に吐き出すためのチューブを装備してるのでその点は安心です♪
・・なわけあるか。

KDX125SRサイレンサー。
一応、サイレンサーを車体から外して丸1日放置したら周囲がオイルだらけになった(´;ω;`)
こんなホースがあろうがなかろうが、
サイレンサーの消音材に含浸した燃え残ったオイルとガソリンの混合液は排気に乗ってサイレンサー後端からも吹き出すに決まってるのです。
※全く効果がないとは言いませんが焼け石に水ってやつです。
ちなみに・・
古い2stは2stオイルの混合率を高めて焼き付き防止にしてたらしいです。
メーカーとしてエンジン焼き付きだけは避けたかったらしい。
HONDAのMVX250なんてサイレンサーからダラダラ燃えカスが垂れてる個体しか知りませんが2stオイルの混合率が高かったからみたいですな。
※MVX250なんて昔は10万円以下で中古が売られてたけど今凄い高いのね。
とはいえ。
KDX125SRのデビューって90年代初期ですよな。
それって2stの歴史だとかなり新しい方なんじゃ・・。
ま、KAWASAKIだからね。
・・KAWASAKIって昔は2st屋だったんじゃなかったっけ?
まあこの時代の2stオフロードバイクの中には純正サイレンサーにチューブが付いてる車種も少なくなかったのでこれがトレンドだったのでしょうねえ。
そりゃ環境性能ゼロだわな(笑)
※よくこんな仕様で8年もの間継続販売されてたな。
それにしてもKDX125SRは初心者に選ばれがちな排気量です。
公道ではもちろん、エンデューロレースに参加する初心者がコース上で全開できるわけもなく、
燃え残った混合液がサイレンサーにたまるのを防ぐ意味はあったのでしょう。
この手のトラブルに対するKAWASAKIの親切心なのかもしれませんな。
サイレンサーのメンテナンスハッチを設けるとかできなかったのかと思うけれど、
高く売ることができない原付2種バイクなので、さらにお金がかかる構造にはできません。
ただでさえいろんなところに無駄に金がかかってるKDX125SRです。
とりあえずチューブ付けておいたので燃えカスは車外に排出しなさいよ、という感じなんでしょうねえ。
※環境問題がいかに軽視されてたかという90年代初頭の設計ですからね。
KDX125SRの純正サイレンサーは分解できない

でも詰まり切った純正サイレンサーは交換するしかないのですかね?
KDX125SRの純正サイレンサーは非分解式ですので内部に燃えカスが溜まったら交換するしかありません。
とはいえ、
新品のサイレンサーはメーカーにも無いハズです。
中古の純正サイレンサーはネットオークションで結構売りに出ていますが、ボロいわりに高い。
それに内部が燃えカスで詰まってないという保証はないのです。
※8割がた詰まってると思って間違いないね。
というわけで困ってるわけですよ。
KDX125SR2号機も1号機のように分解出来て消音材を交換できるタイプの 中古でもすんごい高い 社外品のサイレンサーにするか・・。
それはなんだか負けた気分ですな。
なんとかする方法は無いものか

今それやったら有毒ガスが出まくって怒られそうだな。
※山火事とかになったらシャレにならないし。
2stバイクというのはパイーンという気持ちのいい高回転時の加速が面白さのポイントです。
そのためにはチャンバーやサイレンサー内を綺麗に保つ必要ながあるのです。
ということは内部に溜まった燃えカスを除去する作業が付いて回ります。
これは2st乗りの宿命なのです。
2stは長く乗れば乗るほどその宿命は確実にオーナーに迫ってきます。
※4stに比べてはるかに面倒くさいけれど、それもまたオーナーを選ぶのでヨシ♪誰にでも乗れちゃいけないのよ、2stは。
原則として、
チャンバーやサイレンサーをこじ開けて清掃しない限り、チャンバー内の燃えカスを完全に除去することはできません。
それでも何かせにゃなりません。
どうするか?
焼ききる
燃えカスは燃やしちゃえばいいのです。
とはいえ、
純正のチャンバーやサイレンサーは相当な温度でなければ焼き尽くすことはできません。
※チャンバーやサイレンサーの外側は鉄板が厚いうえ、内壁があるしで外部からの熱伝導は極めて悪いです。
そこで古の2st乗りは、
「チャンバーとサイレンサーをドラム缶で焼く。」
という手法をとってたという記録があります。
※理にかなってるとはいえ、誰がやり始めたんだか(笑)
物凄い高温で焼かねばならないので燃料をどうするかという問題があるのですが、
経験上バンバン建材の廃材を燃やせば行けそうです。
ただし、
チャンバー内の燃えカスが燃えるので環境に非常によろしくないので通報されても仕方ありませんな(笑)
※つくづく環境にはよくないし、田舎でやると山火事にはなりそうでもある。
経験者によるとドラム缶でチャンバーを焼くと内部の燃えカスが燃えてサイレンサー部から火を噴くらしい。
※見て見たくもある。
で。
焼きあがったら完全に冷まし、外側からコンコンと叩くと炭化した燃えカスが排出されるそうな。
※チャンバー内の消音材も綺麗に焼けちゃうらしいけど。
薬液で洗う
ドラム缶方式ではなく、薬液で燃えカスを洗い流すという手法は割と最近でも聞きますな。
「酸性の強い薬液をサイレンサーやチャンバー内に充填させた状態で炎天下に放置する。」
という作戦です。
※薬液は昔から濃い酸性のサン○ールを使うと良い、と古の文献にはある。
効果はありそうですが、
「燃えカスの混合された廃液をどうするか。」
っていうのが問題になりますね。
ただでさえ、
燃えカス入りです。
しかもサ〇ポールは強酸性ときた。
※かえすがえすも2stは環境にはよくないね。
こういうのを下水に流すのは違法だし、そこらへんに捨てるのも違法なハズです。
みんなどうしてるんだろうか?
除草剤として使ってるか、田舎では穴掘って埋めちゃうんだろうな。
帝王切開する
チャンバーはともかくサイレンサーの外壁を切り取って内部を引っ張り出して清掃する。
この作戦も割と良く聞きます。
しっかり蓋が出来ないと水が侵入したり、廃棄漏れしたりしそうだしねえ。
※でも燃えカス排出ホースがあるくらいだから、廃棄漏れはそれほど考えなくてもいいのかも。
ちゃんと蓋が出来ればメンテナンスハッチとして使えそうですが加工の腕がないねえ。
※そういえば金属加工のプロがいるな♪頼んでみようかな。汚れるからやだって断られそうだけど。
社外品のサイレンサーのようにメンテナンスを考慮した作りならいいんだけれど。
純正のサイレンサーは基本的に使い捨てみたいな作りだからねえ。
※使い捨て前提の割にチャンバーやサイレンサーの鉄板は厚くて重くて丈夫なんだよな。
自然に吹き飛ばす
詰まり気味のチャンバーやサイレンサーとはいえ、ぶん回し続ければいずれつまりも取れるハズです。
この手法であれば公道で普通に走ればいいだけです。
一番手軽で現実的な手法ではある。
ただし、
しばらくは白煙をまき散らすことになるでしょう。
※やっぱり環境にはよくない。
一番違法性がなさそうな手段ではあるけれど、後続車両には文字通り煙たがられるし、
KDX125SRでそれをやると余裕でスピード違反になるのでやっぱり違法かもしれませんな。
そもそも同じ場所をぐるぐる回って白煙垂れ流してたらやっぱり通報されそうな気もしています。
まいったね。
オフロードコースに持ち込んで1時間だけ走らせてもらうかなぁ。
※でもオンロードに振った特性のタイヤを履く予定だしなぁ。
ちなみに・・
当倶楽部のKDX125SR1号機やDT200WRは驚くほどサイレンサーに燃えカスが溜まりません。
万人におススメはしませんが オイルポンプを極力少ない方に絞ってるのと、
田舎なので頻繁に低回転で全開に近い状態で走り回れてるからではないかと思います♪
R.S.Vのサイレンサー分解して消音材を見ても燃えカスで飽和状態になっておらず、部分的に白いままだったりするし。
これはひとえに「田舎だからできること。」なのかもしれません。
両車とも91年式で5万キロ以上は余裕で走ってる割にものすごい調子がいいです♪
KDX125SR1号機は最高速はぬうわkm/h出ますし、ツーリングでは燃費は25Km/L以上になることも珍しくないです。
DT200WRは高速道路ではぬふわkm/hで余裕で巡行できますし、オンロードのツーリングペースなら20Km/Lを超える燃費になることもあります。
※DTは 設計上6速のギア比がおかしいので 最高速はなかなか伸びないからやったことないです。でもぬふわkm/hは余裕。
それでも、
当倶楽部の2st勢は定期的にサイレンサーの消音材は交換するようにしています。
※賛否あるけれど消音材には建材用の不燃性の断熱材とスチールウールを加工して針金で巻いています。安くていい♪
まとめ

素人が挑戦できるレベルの燃えカス除去方法というのは無いものか。
とりあえず、
「自然に吹き飛ばす方式。」で進めるかなぁ。
夜の交通量が少ない時間帯にバイパスを流すとかねえ。
とはいえ、
どうしたものか。
サイレンサーやチャンバー内の燃えカスを除去する良いアイデアがあればご教授いただけると幸いです。
※同好の士とこういう情報を共有したいのですよ、ワタクシは。
それ以外にも考えねばならない お金のかかる 項目が山のようにあるのですが、そんな面倒があってもレストアは面白いのです。
長らく続いたKDX125SR2号機のレストアですが、これからあ乗りながら調整というフェーズに入ります。
※レストア完了はまだ遠いのですが。
ちなみに・・
KDX125SR2号機はこの度ナンバーとってきたので公道で走ることができるようになりまして。

KDX125SR2号機。
長野の春を満喫してる・・とはいいがたいけれど花が多いこの時期は橋照って楽しいのも確か。
※でも今年はだいぶ寒いよ。
タイヤがアレなので全開走行はまあまだなんですがね。
空いている時間を選んで割と一生懸命バイパスでアクセル開けてみました。
※とりあえず、運用でチャンバー&サイレンサー内の燃えカスを排出してみようと思ったわけです。
そしたら。
想像通りに後方は白煙の煙幕に(笑)。
※後続車がいなかったのでまあ良しということで。

KDX125SR2号機ナンバー裏。
まあうすうす想像はしてたんですがね。
その結果、リアフェンダーとナンバープレート裏にべっとりと燃えカスが・・。
そのままにしておくと固化して取りづらくなるので速攻で拭き取りました。
で。
何故か点滅を確認したLEDウインカーが点滅しなくなりました。
どうも安物のLED対応ウインカーリレーがダメっぽい。
バッテリーレスでも大丈夫な仕様ということで買ったのに一発で壊れマシた(´;ω;`)
もう一回他のウインカーリレー買ってそれでもダメなら電球に戻すかな。
こんな記事もあります▼