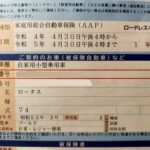特に2stはその寿命が短いです。
今回、DT200WRとKDX125SRのR.S.Vサイレンサーの消音材を交換してみました。
消音材は100円均一のアレを使ったりしています♪
作業自体は簡単ですが手間はかかります。
マフラーのサイレンサーの中身はなんだ?

ばらしてみるとわかりますが、
基本的に排ガスを消音材にくぐらせて消音しているだけです。
バイクの純正マフラーはサイレンサー内部で入り組んだ流路で排ガスを流して音を消しています。
このため「抜けが悪い。」とか言われます。
※実際に内部構造を見るとこの複雑な構造であれだけ抜ければ十分な気がします。
社外品のマフラーの多くは直管にグラスウールを巻いただけのシンプルな構造です。
そりゃ抜けもいいわ。
したがって。
サイレンサーを持つ市販品のリプレイスマフラーに交換するとエンジンの吹け上りが軽くなるのです。
※一流チューナーのマフラーでも高回転時はともかく実用域でのトルクは減ってたりするんですがね。
ソレはソレとして。
基本的に純正マフラーのサイレンサーの消音材は交換することができません。
多くのマフラーは「非分解式。」になってるためです。
これは、
ワタクシたちの先輩たちが爆音仕様にするため、サイレンサーを外しまくった挙句、
さんざんやりたい放題やったため、
「サイレンサーは非分解式にせよ。」
と、お国からメーカーに対してお達しがあったらしいのですよ。
※それでも馬鹿どもはマフラーぶった切ったりするので意味はないのですがね。
ということは。
純正マフラーの場合、サイレンサーが煤などで詰まったら丸ごと交換するしか手はない、ということです。
※「サイレンサーを切開して内部の消音材を交換する。」という剛の者も昔からいますが溶接スキルが必須です。
当倶楽部でも、セロー225Wの純正マフラーから黒煙を吹く現象が起きましたが、
この原因はキャブが濃いセッティングだったわけではなく、マフラーの内部にすすが溜まってたことが原因でした。
しばらくぶん回して乗ってたらいつの間にか煤が出なくなったのでヨシとしていますが、本来はサイレンサーの交換案件でしょうねえ。
※結局、根本的な解決になっていません。
また。
KDX125SR2号機のサイレンサーから燃え残ったオイルが垂れる現象も発生しています。
この原因もサイレンサー内部で燃え残ったオイルが飽和量を超えたため、垂れ流しになってると推察されます。
※サイレンサーからオイルが垂れるのがKDX125SRに対するKawasakiの仕様、となっていますがメーカー問わず昔はみんなこんなでした。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼
ワタクシは耐久性や消音能力、パワーと燃費のバランスを考えて基本的には純正マフラーが好きです。
実はマフラー内部の消音材は「消耗品。」です。
基本的に純正マフラーの場合は前述したとおり、
内部が排ガスのカーボンが溜まったり、燃え残ったオイルが溜まりすぎたりして、
マフラーから黒いカスや液体が飛び散るようになったらサイレンサーそのものを交換するしかないのです。
が。
古いバイクで純正マフラーが入手できない場合もあるのです。
その場合、次善の策として極力静かなリプレイスマフラーを選択することもあります。
サイレンサー内部の消音材が消耗しただけでマフラーごと換えるなんてもったいないからです。
構造が単純なリプレイスマフラーになかにはサイレンサーが分解できるものがあります。
そういうタイプのマフラーは内部の消音材を交換できるのです。
※お国の指導はどうなってんだろうね。おそらくレース用品として公道使用不可だと思うけど限りなくグレー。
マフラー自体が錆びたり凹んだりしなければ永久に使えるわけですよ。
※リプレイスマフラーは絶対錆びますが。Z1系のKERKERなんてステンレス製のくせに錆びますよ。
2stの場合はサイレンサーだけ交換することもできます。
※2stオフ車用のリプレイスマフラーの薄い金属製のチャンバー部は圧倒的に耐久性がないし、カンカンうるさいので嫌いです。
当倶楽部では、
のサイレンサーは消音材が交換できるものになっています。
いずれも数十年前のバイクなので純正が手に入りませんので仕方なく、です。
今回の記事はそういうバイクのサイレンサーの消音材を たまには 交換してあげようって話です。
こんな記事もあります▼
2stのサイレンサーは燃え残ったオイルのために4stのそれと比べると劣化が早い傾向にあります。
なので、
今回消音材を交換するのはDT200WRとKDX125SR1号機です。
いずれも純正チャンバーにR.S.Vサイレンサーの組み合わせとなっています。
これらは比較的簡単にサイレンサーの消音材の交換が可能です。
ちなみに・・
この不景気なのに不具合のない純正マフラーを社外品に交換をする人が多いのは謎ですな。
マフラーを交換しても大して性能あがりゃしませんよ。
※少なくとも数十万円かけただけの性能アップはないです。
最近は車検で普通に排気音量の計測がされてるし、
警察の皆さまも音量規制で本気になろうかというこのご時世に、
わざわざお金を捨ててまで 純正マフラーを変える人の気持ちがよくわからん。
※改造やカスタムは下取り時に買い叩かれるのでさらに損ですよ。
みんな爆音が好きなんですかねえ。
うるさいバイクは疲れますよ。
まあこれも趣味っちゃ趣味なので好きにやればいいのですが、
爆音バイクは確実にうるさいと思ってる人がいるということをお忘れなく。
こういうことを守らないのでバイク乗りが軽視されるんですよ。
※近所から白い目で見られても平気なのかしら?
今も昔も爆音を立てるバイクなんて昔っからダサい代表みたいなもんです。
当人たちがいくら否定しても珍走団と変わりませんわ。
※峠でとんでもないスピードで暴走する爆音車両のどこが珍走団じゃないっていうのか説明してもらいたいわ。
いつまでたってもバイクの社会的地位が上がらないのは
違法改造する奴らが大量にいるのが原因の一つだと思うのです。
それを善良そうな顔をした中高年ライダーが得意げにやってるのが情けない。
そういうのは小僧がやるからまだかわいいんですよ。
中高年はもっと分別があってしかるべきです。
そもそも。
リプレイスマフラーに交換した後、全然使える純正マフラーはどうしてるのよ?
邪魔じゃない?
それに無駄じゃない?
※SDGsって知ってる?
こんな記事もあります▼
2stのサイレンサーの消音材は燃え残ったオイルで消耗が速い

サイレンサー内のグラスウールを燃え残ったオイルが満たしちゃうからです。
新品のうちはまだしも、
2stエンジンのバイクは公道で使い続けるとどうしてもサイレンサー内に燃え残ったオイルが溜まります。
エンジンを常にぶん回してサイレンサー内の燃えカスを 吹っ飛ばす 焼き切るのが効果的ですが、
公道を走る以上、免許を考えるとなかなか難しいのが現状ですな。
田舎だと結構ぶん回せる峠とかあるため、オイルの燃えカスが溜まりにくいのですが、
都市部で使う2stバイクのオイル燃えカスはサイレンサー内でかなり強烈に溜まってるはずです。
※高速に乗れる車種なら1区間だけ1速落として全開!とかやるとかなりきれいに焼けますがおススメしません。
サイレンサー内に燃えカスオイルが溜まってるバイクの後方には黒い燃えカスオイルが飛び散るのですよ。
この黒い染みは白いウェアについちゃうと二度と落ちません。
白煙は巻き上げて乗ってるライダー自身にも降りかかりますので背中は真っ黒になります。
当然、後方にはさらに多くの黒い粒が飛んできます。
そんなバイクでツーリングに行くと、後続の車両から非常に嫌われます。
※昔からマスツーリングでは2stは最後尾が定位置です。
消音材が燃え残ったオイルで満たされちゃうと消音能力の下がりますしね。
ゆえに。
2stは定期的にサイレンサー内の消音材(グラスウールなど)を交換する必要があるのです。
アイドリングが長かったり、渋滞を多く走ったり、高回転を使えなかったりする場合、
長くても1万キロも走れば交換すべきと思います。
※都市部の2st乗りは大変。
が。
80年代前半に、
「サイレンサーは分解出来てはいけない。」
というお国からのお達しがメーカーに対してあったようでして。
次第にメンテナンスが必要なはずの2stのサイレンサーは非分解式が当たり前になっていきました。
そういう車種はサイレンサーを丸ごと交換することになり、高額な出費となりました。
というわけで。
多くの 貧乏な 2st乗りはサイレンサーのメンテナンスをすることなく乗り続けたのです。
80年代の街中や峠には排気口から黒いオイルの燃えカスが駄々洩れしてるようなバイクはたくさんいたのです。
これは消音材を交換すべき時期の目安なんですが 貧乏なので ガン無視です。
その結果、
「2stは汚いもの。」
として世間に認知されることになるのでした。
ちなみに・・
RZ250やRZ250R(ビキニカウルの初期型)の 葉巻みたいな形状の チャンバー一体型のサイレンサーはまだ消音材を交換することが出来たのです。
※マフラーエンドの下についてるプラスねじがオイルだらけで外しずらいんですが。

初期型RZ250R。このぶっきらぼうなチャンバー、素敵すぎる
この頃までは「公道用の2stなんだからサイレンサーの消音材は定期的に交換してね?」というメーカーの良心があったのでしょうねえ。
が。
レプリカ時代に入ると「サイレンサー別体式チャンバー。」が流行ります。
見た目がレーサーっぽいので人気を博しましたな。
※初期のサイレンサー別体式チャンバーは抜けが悪くてワタクシは嫌いでしたが。
この頃、サイレンサーは非分解式になったと思われます。
当時のバイク乗りは たいてい貧乏なので サイレンサーを分解メンテするような人はほとんどいなかったんじゃなかろうか。
当時の唯一の情報源だったバイク雑誌でもそういう特集は記憶にありませんし。
ゆえに。
消音材にたっぷり燃えカスオイルを含んだため、サイレンサーの消音機能が消滅して、
純正チャンバーなのに騒音規制値を超えちゃうRG250γとかいたわけですよ。
今ではいい笑い話ですが。
決しておススメしない自作のサイレンサーの中身

これがなかなか手に入りにくいんですよ。
それなら代用品で何とかするのが当倶楽部流です。
社外品のサイレンサーには交換用のグラスウールを商品化してくれているところもありますね。
当倶楽部のDT200WRやKDX125SR1号機についているR.S.Vにも消音材のパーツだけの供給があったと記憶しています。
※専用品は気分がよろしいんですが恐ろしく高いので手が出ない。
ただし。
2stが売られなくなってから数十年経過した今となってはそんな部品は流通していないのですよ。
※デッドストックがあってもすごく高い。消耗品は安くあってもらいたい。
で、だ。
当倶楽部ではマフラーの消音材には代替品を使っています。
グラスウールは建材用を使用。

建材用のグラスウール。
念のため、部分的にバーナーであぶって燃えないことを確認してます。

ステンレスたわし。
カサ増し&補強としてステンレスたわしを使用。
これが非常に具合がいい。
もう何十年もこの作戦です。
ちゃんとやれば音量は普通の人間が聞いてもほとんど大きくなりません。
※Z1-RもZ750D1のサイレンサーにもこの消音材を使用しています。当然ですが普通に車検に通る音量です。

サイレンサーのバッフル基本形。
Z1-Rのサイレンサー部。
綺麗に加工してるけど元は建材です。
ちなみに・・
2stはオイルが切れるとエンジンが焼き付きます。
メーカーはこれを嫌って2stオイル供給量は多めになるようにオイルポンプのセッティングをしてたようです。
※マニュアルの設定どおりだと大抵オイル量が多いです。絞るのは自己責任で。
「焼き付くくらいなら、オイルで汚れたほうがマシ。」
という思想でしょうねえ。
※あのエンジンは焼き付く、とか言われるとクレームになるしね。
普段からエンジンを回せる人ならオイルはちゃんと焼き切れるのですが街乗りをする公道用バイクです。
どうしても常にオイル供給が多めになります。
※アイドリングが長かったり、渋滞でストップ&ゴーを繰り返すと如実に燃え切らないオイルが増えます。
そうなるとたまに使う高回転時にはマフラーから白煙を撒きまくり・・ということになるのです。
普段高回転まで回してない2stエンジン搭載のバイクで高速道路を走行すると後方大変なことに(笑)
※煙幕、とか言われる。
普段からちゃんとエンジンをぶん回して走ってる調子のいい2stバイクは白煙はそれほど多くないのです。
そういうバイクのサイレンサー内の消音材は意外と綺麗なのですよ。
※こういう所でオーナーとバイクの付き合い方がわかっちゃったりするのです。
作業自体は簡単だけど

せっかくなので同時に清掃もやっちゃいます。
R.S.Vサイレンサーの中身は円筒状のパンチングメッシュ材にグラスウールを巻いただけ、というシンプルなもんです。
※社外品のサイレンサーは大抵こんなつくり。純正はもっと複雑で凝っています。
サイレンサーを分解して内容物を取り出します。
以前交換したステンレスたわしとグラスウールが出てきます。

2stのサイレンサーの中身。
普通にこれくらい汚れています。
これでもすごくマシな方です。
※ひどい奴はオイルが滴っています。
その中心にはステンレスのパンチングメッシュ材が入っています。
パンチングメッシュ材の穴から排気が消音材に吸収されることで消音しているということです。
引っ張り出した消音材は5年くらい前に交換した記憶があるので、その後少なくとも数千キロは走っているはずですが綺麗なもんですな。
※ステンレスたわしはさすがに燃えカスのオイルでコーティングされて真っ黒になっていますが。
それでも、
交換してから数千キロは走ってるのでパンチングメッシュの穴がオイルの燃えカスやカーボンなどで埋まっている箇所もあります。
一個一個の穴をキリを使って清掃していきます。
※ワイヤブラシとかで擦っても無駄ですし、バーナーで焼くのは熱すぎる。パーツクリーナーだと周りが汚れまくるのでこの方法が最も確実で速いと思います。

サイレンサーの中央のパンチングメッシュ。
コレもすごくまともな方です。
※ひどい奴はオイルでべとべとです。

サイレンサーのパンチングメッシュを清掃中。
キリを使って穴を一個一個ほじくっていきます。
固化したオイルやカーボンがポロポロ落ちていきます。
※カスが固形ではなくベトベトしてる場合はオイルが燃え残ってるということです。
綺麗になった円筒状のパンチングメッシュに「ステンレスたわし。」を適当に巻きつけます。
※たわしの中央に穴をあけてそこにパンチングメッシュを通していくイメージです。
この辺は適当です。
その上から建材用のグラスウールを巻きつけます。
※配管用のだと中央に穴が開いてて使いやすいです。昔はグラスウールの断熱マットを丸めて使ったもんですが。
これも適当です。
これらの作業は薄手のゴム手袋があるとよろしい。
手袋内が汗だらけになりますが手がオイルで汚れることなく作業できます。
※グラスウールはチクチクするし、人によってはアレルギー起こすからね。
で。
最後にサイレンサーを元通りに組み立てれば完成です。
※R.S.Vのサイレンサーの組み立てのポイントは円筒形のパンチングメッシュが刺さる箇所が楕円形の中央ではない、ということです。
サイレンサーの中身は綺麗だったので軽く乾拭きした程度で終わりにしました。
※どうせ外からは見えないし、きれいにしてもすぐ汚れるのは明白なので。
念のため、エンジンを始動して
を確認します。
作業はともかく、用意するものは一緒なので複数台やっちゃったほうが効率がいいです。
※2台やっても2時間かからないくらいの作業時間です。
そうそう。
ステンレスたわしは100円均一で入手したものです。
どうせ消耗品なのでこれでいいのです。
グラスウールは近所のマニアックなホームセンターで買った汎用的なものです。
たしか600円くらいでした。

内径をチェックしてから購入しよう。
サイレンサー内部のパンチングメッシュ管の径に合わせないとめんどくさい。
そうそう。
当倶楽部ではサイレンサーの消音材として使っているステンレスたわしですが、
似てるからと言って「スチールウール。」を使ってはいけないのです。
※「金属たわし。」とかいう名称で100円均一でも売っています。
一見、加工しやすいし安いし たわしとしても超優秀だし 良さそうなのですが、
消音材として使うとサイレンサー内で猛烈に錆びます。
スチールウールは水につけて一晩経つと錆びています。それくらい錆びやすいです。
錆びると掃除が大変だし、いいことは一つもありませんよ。
それに。
スチールウールは意外と簡単に燃えるんですよ。
ライターで炙ると割とすぐに火が付きます。
オイルが付着すればスチールウールはさらに燃えやすくなると思われます。
走行中のバイクから発火!とかなったらシャレになりません。
この辺は自己責任ってやつです。
無料のネット情報を参考にして 自分のアレンジを加えてるくせに 人のせいにしてはいけないのだよ。
ちなみに・・
KDX125SR1号機のサイレンサーには当時もののR.S.V純正の消音材が入っていました。
あの頃は普通にバイクショップで買えたんだよなぁ。
今となっては貴重品ですが再利用はできませんな(笑)
とはいえ、
この消音材は少なくとも5年以上前の代物です。
飽和していないとはいえ、燃え残ったオイルをかなり吸っていますので、躊躇なく更新します。
消音材がパンチングメッシュと接触している箇所は燃え残ったオイルが固化して層になってるようで、
これ以上燃え残りのオイルを吸いませんな
道理でKDX125SR1号機はサイレンサーの排気口からオイルが染み出すわけだわ。
これでしばらくはサイレンサー付近のオイル垂れ問題に悩まされずに済みそうです。
が。
2号機はオイル垂れがもっとひどいのですが、消音材が交換できない純正サイレンサーだしなぁ。
※苦肉の策としてサイレンサーからホースを生やして車外に排出するのがKDX125SRのKawasaki純正の仕様です。他社も似たようなもんでしたが。
多分、サイレンサーの中はとんでもないことになってるんだろうな。
予備のサイレンサーが手に入ったら帝王切開してみようかねえ。
でも純正のサイレンサーって結構肉厚なんだよねえ。
※純正のマフラーは耐久性を上げるため、いろんな工夫してあるからねえ。
中古のR.S.Vのサイレンサーなんて超高級品になってるしなぁ。
※既に生産終了から四半世紀経過した社外パーツをあんな値段で買う奴いるのかね?
こんな記事もあります▼
まとめ

これでしばらくはオイル垂れ問題から解放されそうです。
サイレンサー内のグラスウールを交換したら吹けが良くなった気がします。
※多分にプラシーボ効果があるとはいえ、排気音がカリンカリンと軽くなるのは気分がよろしい。
現在、当倶楽部の2stエンジン搭載バイクは非常に調子がいいです。
DT200WRは驚くほど白煙を吹きませんし、十分実用に耐えます。
※多少オイルポンプを絞ってるのと低回転でぶん回してるからだと思われます。
KDX125SR1号機は Kawasakiにしては 非常に優秀で燃費もいいし、馬力もある。
原付2種のくせに あっという間に制限速度に達します。
特に動力性能や消音性能に問題があったわけでは行けれど、数年ぶりに消音材を交換してやったので気分がよろしい。
KDX125SR2号機は恐らく大量に燃え残ったオイルがサイレンサー内残ってるのでオイルが垂れますが、こういう仕様なので仕方ないのかもしれませんな。
※サイレンサーを切開して何とかしてみようかとも思うけれど、中古で程度の悪い純正サイレンサーすら数万円するのが現状なので躊躇してるのですよ。
もう一度書きますが、
サイレンサー内の消音材どんな素材を使うにしても、しっかり自分で燃えるかどうか確認をしてから使いましょう。
こういうのはネットの情報をそのまま鵜呑みにしちゃだめなのです。
ネット民は無料の誰かが言った自分に都合のいい信じたい情報を勝手に鵜呑みにしがちです。
ワタクシは一度も発火したことはないし、運用上問題が起きたことはありませんが、
劣悪な素材や運用の違いによっては何が起こるかわかりません。
自分で試すしかないんですよ。
こういうのが自己責任っていうやつです。
当ブログは基本的にワタクシの実体験を書いていますが、
それだってやりようによっては危ないことだってあるのです。
※細かいコツとかポイントとか書ききれないことも多いし。
そもそも。
ネット上の無料の情報を信じすぎです。
流行のAIだって、2025年9月の時点で嘘ばっかりですからね。
※Googleなどの検索の一番上にAIの回答が出ますが結構適当だったりします。
情報が都合よくネットに無料で転がってはいないのです。
※あったら有料になっていますよ。
サイレンサーの消音材の件も自分で素材を確かめてからやるといいでしょう。
※そのほうが自分の知識になるし、いい経験になると思います。
なんでも簡単に済ますのではなく、なんでも実現するまでの試行錯誤や考える工程が面白いのですよ♪
ちなみに・・
2stはエンジンの基本的な構造上、ある回転域でしかパワーが出ないんです。
なので、古い2stバイクは「高回転。」でだけ、バキーンとパワーが出るピーキーな性格になりがちです。
ただし。
Y.P.V.Sのような可変バルブシステムを組み合わせて広範囲の回転域でパワーが出るように進化していきました。
なので、
80年代中盤以降の2stは意外なほど低回転でもトルクがあったりします。
※ワタクシの大嫌いな電子制御が入ると2stは劇的に変わるのよ。
という特徴がありバイクのエンジンとしては4stエンジンより優れている気がします。
※世界GPは2st500ccが最高!と思ってるワタクシと同年代のバイク好きは多いハズ。

DT200WR。
特に2stオフ車は誰にでも気軽に乗れるバイクではないのがグッとくるのよ。
林道で楽しく走るにはそれなりのライディングテクニックを要求されます。
※慣れないと怖いしかないです。
それでも2stエンジン搭載車は、
というネガな部分が多いのも確かです。
基本的にはメンテナンスしないと寿命が短いのが2stですが、
オーナーが無知なため、乗りっぱなしで放置された個体が多いのです。
実際、現存車輛はどんどん減っているようで2025年現在、休日でも街中で2stエンジン搭載車を見かけることはほとんどありません。
※有名なツーリングスポットでも見かけることは皆無です。
既に2stエンジンを整備できる人はかなり減っているようですし、
中古を組み合わせれば不動車でも何とか復活できるかもしれませんが、
パーツ不足でそれもだんだんきつくなりつつあります。
恐らく2stエンジン搭載車は環境問題やメーカーの開発費低減などの理由で、二度と商品化されることはないと思われます。
バイク乗りとして1度くらいは2stエンジン搭載車に乗ってもらいたいもんですが、
今となってはそれも簡単にはかなわない世の中なのです。
2stは多くの伝説を作った名機が多く、中高年ライダーにとっては夢のバイクだったりします。
でも、多くの若いライダーには「2st?何それ?」となりつつあるのですなぁ。
2stは大枚はたいて購入したとしても、すでに四半世紀以上前の乗り物です。
もうすでに機械としては末期です。
「2stバイクを買うのはやめておけ。」
というのがワタクシからのアドバイスです。
現時点でも維持は大変です。
壊したらパーツがないので二度と直らないリスクがあります。
直してくれるショップもほとんどありません。
こういう覚悟がないなら、できるだけ新しい車種にしておきなさいってことです。
※外国のバイクと同じかそれ以下のレベルでパーツがないです。
それに。
2stバイクが走るのに必要な2stオイルの価格上昇はひどいもんです。
2025年9月現在、長野のホームセンターでは1800円/Lくらいします。
2stオイル代は維持費に直接かかってきます。
まだ購入できるだけマシとはいえ、今後需要が増えることはないので供給量が減り、値段が高騰するんでしょうねえ。
※ほんの数年前まで1000円しなかったんだけれど。当倶楽部では SUZUKIのバイクが一台もないにもかかわらず、 SUZUKIの純正を使用しています。
いずれにせよ、現在は2stが生き残るには厳しい時代になっているということです。
現オーナーは大事にしましょう。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼