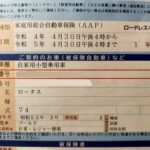何が起こるか読めないし、読めたところでどうしようもないし。
でもライダーは誰でも最初のツーリングを経験してるはずなのです。
でもポイントはある。
当倶楽部流の最初のツーリングのポイントを伝授しようではないか。
誰にでも最初はある

街中で見かけるすべてのライダーにも最初のツーリングがあったはずなのです。
いよいよツーリングに出られるとしましょう。
数々のハードルを乗り越えて、ようやくスタートラインに立つわけです。
でも最初のツーリングってめちゃめちゃ不安なんですよねえ。
今ではへらへら日本の端っこまで行くのもあんまり躊躇しないようになったワタクシも、
大昔にはそういう思いを持ったことがあるのですよ。
※最近は遠くまで行ってませんが。

Z1-R。
単独行だと意外なほど短い時間でも充実したツーリングになったりするのだ。
バイク乗りは単独行にこそ、真髄があると思うのだよ。
というのも。
バイクというのは基本的に自己責任なのです。
何かがあってもなくても、一人で何とか対処せねばなりません。
何が起こるかわからない上に、なにかあったときの対処が上手くできるかどうかが不安なんですよねえ。
まあ大抵は「何もない。」のですが。
※無事これ名人の精神で走り続けていれば大きなトラブルには合いにくいですよ。
基本的にソロツーリングをするライダーは超慎重です。
ソロライダーは面倒くさいことを避けるため、何事も起き無いような安全運転をキープするものです。
※大抵トラブルを起こすのは群れて調子に乗ったライダーです。
ただし。
その安全域の匙加減というのが難しいのですよ。
最初のツーリングには何をもっていけばいいか、とかそいうのは別の記事にするとして
当記事では「バイクに慣れるまでのツーリングでのルートの考え方。」を書いてみようと思います。
おせっかいだと思うのですが 今まで、そういう切り口で書いてある記事を見たことないので。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼
最初のツーリングのポイントは国道

慣れてくればどこにでも行けるのです。
最初のうちは「バイクで公道を走ることに慣れる。」ことに全力を傾けるべきだと思っています。
バイクの初心者は周りの交通の流れに合わせるだけでも大変です。
信号毎に初心者が苦手なハンクラを使わねばなりません。
※最近のバイクはスタート時にエンジン回転が上がるってホント?
走り出したとしても走行中に、
いきなり飛び出してくる人や自転車、お年寄りの運転する軽トラなどを警戒せねばなりません。
物陰に潜んでいる白バイや道路に出てきがちな野生動物にも注意を払わねばならないのです。
※最近の公道は 想像力の欠如した自分勝手なドライバーやライダーが多いので 軽めのマリオカート並みに危険だと思っていいです。
バイクは全力走行していなくても周囲への警戒を考えれば、いつだって100%の注意力が必要なのです。
実際、めちゃめちゃ忙しいんですよ、公道のバイク乗りは。
それに加えて、停止時は単独では立ってることもできないのがバイクです。
休憩時にはバイクを押し引きせねばなりません。
坂道に頭を下にして止めてごらんなさい。
引っ張り出すのだって一苦労なのです。
バイクのツーリングは停車時だって休憩時だって気を抜けないのです。
※休憩時に缶コーヒー飲んでても、面倒くさい話好きの爺につかまることだってあるのです。
バイク初心者は走っても止まっても気を抜くことができないと思いましょう。
誰もみんなそういう経験をしてベテランライダーになっていくのです。
こんな記事もあります▼
このように。
いろんなピンチがあるのですが、ピンチな状況にあっても誰も助けてくれませんよ。
イチイチ対処できるようになるまではそれなりの経験が必要です。
そういう経験を何度かして、余裕でクリアできるようになれば中級者だと言えます。
※ライテクの上達とかは公道に慣れてからでもいいのよ。
とにかく。
初心者のうちはバイクに慣れるまで、
「いろんなことを考えすぎてツーリングルートにまで頭が回らない。」
というのが正直なところでしょう。
多くのライダーは アホなので そんなに器用ではないし、頭の回転も速くないのです。
というわけで。
最初のうちは「わかりやすい国道をメインに走る。」ことをおススメします。
確かに国道は交通量が多かったり、流れが速い場合もあります。
でも、道に迷わないという点については文句なしです。
大抵、道先案内の青看板があるのでそれに従って行けば、間違えることもないハズなのです。
※ツーリングまっぷるの赤い線の道ですよ。

長野県道133号。
こういう看板があるようなさびれたルートは初心者には少しばかり早いのだ。
初心者の場合、
「道を間違えて迷うことでパニックになっていつもの判断と行動ができなくなる。」
のが何より怖いんですよ。
※実際はリカバリすれば大したことないんだけれど、初心者のうちは大ごとに思えるもんです。
なので。
「国道で行って国道で帰ってくる。」
というわかりやすいルートを考えればよろしい。
紙の地図を広げてみると、自分の家から周遊できる国道ルートがあったりします。
※スマホの地図は部分的に見るのは便利だけれど、大まかな全体像的なルートを決めるには不向きです。
こんな記事もあります▼
国道を利用した周遊ルートが組み立てれれない場合、
同じ国道を往復するだけでも練習にも慣れにもなるのです。
広い公園とかの駐車場、大きめのスーパーやパチンコ屋さんなどでUターンしてくればいいのです。
※念のためバイクを降りて取り回ししましょう。練習だと思えばいいです。
国道がない都内の場合は○○街道とか○○通りを走ればよろしい。
交通量は多いけれど青看板の案内は細かく出ていますので。
というわけで。
初心者のうちは「どこに行くか。」というよりも、
さっさとバイクや周囲の交通状況に慣れちゃうことを優先するといいですよ。
ツーリング先として行きたいところは後でいくらでも行けますので。
※せっかく行きたい場所についてもぐったりしてて、あんまり楽しめないしな。
まあそれでもターニングポイントとして美味しいお店とかをセレクトするのはあり。
※でも出先でお腹いっぱいになっちゃうと注意力が散漫になりがちだし、バイクに夢中になってると言うほどお腹は減らないもんですよ。
とにかく。
初心者のうちは国道メインでぐるっと回って帰ってこれるルートを策定するのです。
国道であればトラブルがあっても 県道とかよりは 交通量があるので人に頼れる場合も少なくないですし。
※田舎にはトラブル時の生命線であるスマホの電波が届かない県道は山ほどあるのよ。 人気がない道はクマも出るしな。
そうそう。
スマホはバイクに固定してナビ的に使って、
落として壊しちゃうとか雨に濡れて壊れちゃうとかするよりも、
ウエストポーチや上着の内ポケに入れておきましょう。
休憩時にバイクを降りて現在位置を確認するのに使えばよろしい。
走行中にスマホばかり見てるとせっかくのバイクツーリングの経験値が上がりにくいもんです。
※スマホの画面を見てるより、道路状況や周りの景色、いろんなことに注力するほうが100倍経験値が上がります。
これはマスツーリングばっかりやって、人の後ろばっかり走ってると道を覚えないのとよく似ています。
※バイク歴はそれなりに長いのに単独行できないライダーは大抵これです。
ちなみに・・
ワタクシの初心者の頃はバイクブームでして。
免許取っていきなりガンガン峠に行く、というのが普通でした。
※バイクの先輩方と出かけると有無を言わさず、峠に連れていかれたのです。
峠を走らねばならない、みたいな強迫観念があってツーリングのたびに毎回どっぷり疲れたもんです。
初心者なので下手くそなのはもちろん、余裕なんか全然ないもんだからずっと路面を睨んでアクセルを開けてまして。
※慣れないうちはフロントタイヤが滑りそうな気がするんだよねえ。
ツーリング後に家に帰って布団に入り、目を閉じても瞼の裏でアスファルトが浮かんだものです(笑)
そういうツーリングも面白かったのですが、
バイクの面白さのほんの一部であると気が付いたのはかなり後になってからです。
バイクの面白さはスピードだけではないのです。
面白いと思う速度域も、面白そうだと思う道も人によって全然違うんですよ。

KDX125SR。県道393。
こういう道も面白いのだけど、転倒したら助は来ないのだよ。
※県道だけどガードレールないし、落ちたら崖だしね。
自分の好きなペースで好きなところを走れるようになるのが最初のハードルです。
誰に合わせるわけでもなく、自分の基準として楽しいと思うペースを理解するのです。
これができるようになると、単独行の楽しさが倍増します♪
脳内で地理を考える

イチイチスマホ見てないで自分で考えたツーリングのルートのどの辺にいるのか?を脳内の地図で把握する練習をしましょう。
ツーリングが始まったら地図を見なくていいわけではありません。
脳内でルートを決めたときの地図を広げて、脳内の地図で自分の位置を確認しながら走るといいですよ。
イメージトレーニングという奴です。
とはいえ。
国道を走る限り、現在位置なんてのはザックリわかればよいのです。
※林道だとそうはいかない場合もあるけど。
車の流れに乗って走りながら
など目に入る情報を頭の片隅に入れておくのです。
※ワタクシくらいになると個人宅に止まってる車種とかも覚えてたりします。
これをやると、
「良く使う国道と自宅の位置と時間の関係を把握できる。」
ようになるのですよ。
ツーリングの帰路で「ここまで来たら自宅まであと30分だな。」とか、
計画時に「ここまでで大体1時間だな。」とか、
そういう距離と時間の感覚を身につけられるってことです。
これを練習しておくと、
国道ツーリングを卒業して県道や市道などのバリエーションを増やす場合に超役に立ちます。
紙の地図と合わせて考えると一日で走れる距離と必要な時間をざっくりと計算できるようになります。
※バイク乗りは無茶なツーリング計画を立てがち。短時間で長距離を走れても別に偉くないのよ。
とにかく。
バイクで走り出したら走行中は地図を極力見ない。
※そもそも走行中に紙の地図を見られるようになったら、ベテランの粋です。
脳内で紙の地図と現在位置を合致させて次の曲がる交差点までどれくらいとか距離と時間の練習をするのです。
これをやると、
「道を覚える。」
んですよ。
地理感覚が脳内ではっきりわかってると抜け道もたくさん覚えます。
将来、マスツーリングする際に、みんなが知らない抜け道をサラリと先導するのだよ。
バイク乗りは道に詳しいほうがカッコいいのです。
※たまに間違えるとしても、だ。
ちなみに・・
今と違ってスマホなどのガジェットがなかった昔のバイク乗りは全員紙の地図しか見てなかったのです。
それしかないので仕方なし。
タンクバッグに折りたたんだ地図(主にツーリングまっぷる。宣伝しておいたのでRちゃんなんかくれ。)を見てましたな。
※大昔のツーリングまっぷるには新潟の記載がないのだが(笑)
国道ならまだしも、県道には青看板の道案内がない場合も多いのですよ。
目的地に近づくため、県道などの脇道に入りたい場合、
信号待ちなどで停止中に、次に曲がる交差点をざっくりと覚えて、そこを勘と経験と度胸で曲がったりしたのです。
※現地点は地図のどこなのかを一瞬で把握する能力が超大事。
当然、現在位置が把握できる手段はありません。
道を大きく間違っても気が付くまでに時間がかかったりしたのです。
現在位置を瞬時に把握できるGARMINの携帯GPSが出た時には、たまげたもんです。
その発展型がスマホのGoogleMapだったりするのですが便利すぎて邪道、と言ってる中高年ベテランライダーは意外と多いのです。
※昔っからのナビを使わないライダーは多少ッと周りでも国道主義者が結構多い。
こういう軽度なトラブルはあったほうが道を覚えるし、あとで思い返したときに思い出深いツーリングになったりするのです。
迷ってこそツーリングなんですよねえ。
※人生と同じです。
ワタクシは 決断力のある方向音痴なので 星の数ほど道を間違えていますが、
イチイチ迷った場所を覚えてたりします。
20年前に迷った道とか普通に覚えていますしねえ。
ナビを使うのはもったいない

でも。
スマホのナビに頼っては走るだけだと、道をトレースするだけのツーリングになってしまいます。
それはすごくもったいないと思うのです。
ナビを使うといろいろ考えなくなるのですよ。
ナビに従って走るだけだと敷かれた線路を走ってるようなもんです。
極端に言えば、ナビに頼るとツーリングの大冒険的な要素がまるっと消えるということです。
なにより。
せっかくバイクで走ってるのにずっとスマホの画面見ながら走るのはもったいないのです。
※結局どこに行ったのか、どうやって行ったのかを覚えないし。
ナビは、
という場合のみに有効であるとワタクシは思っています。
・・これって自由なバイクツーリングの真逆な気がするのですよ。
バイクのツーリング用のナビに大金をかけて装備するのが流行っていますが、もったいないと思っています。
ツーリングで道に迷ったっていいんですよ。
本当に迷ったら現地人を捕まえて道を聞けばいいのです。
流行でナビを搭載しているライダーが多いですが、
ハンドル周りにごちゃごちゃついてるバイクで峠を楽しく走ることなんてできませんよ。
とにかくケーブルが邪魔ですし、視界に入るスマホがうっとうしい。
※低いハンドルのバイクなんてスマホが超邪魔だと思うんですが余計なお世話ですな。
セパハンのバイクだとこの手のハンドルマウントガジェットは全部邪魔な気もします。
※当倶楽部だとVT250FHにGARMINつけるとちょっと邪魔。角度可変マウントアームでかなり楽になったけど。

GARMIN GPS。
モデルごとにしっかりバイクにマウントできるアタッチメントがRAMから販売されてるのがすごい。
まあGARMINのハンディGPSも似たようなもんかもしれませんが、
一応地図は出るけれど、あくまでもあと標高と時計と走行距離、現在位置しか教えてくれません。
※県道レベルだと道路だって表示されないしな。
ツーリングではGARMINのGPSくらいの「ヒントというか指標が出れば十分。」だったりします。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼
ちなみに・・
文明の利器になるべく頼らずにバイクに慣れた人のほうが後々応用が利くっぽいです。
最初からスマホ搭載してると、
「スマホがないと走れない。」
ということになりかねないってことです。
それくらいスマホって依存度が高いもんらしいねえ。
電波さえ拾えれば何でも表示できるしね。
でもさ。
ツーリング中の休憩時、いちいちスマホ外してる?
これってETCと同じように「盗まれるリスクが超高い。」と思うのだけれどどうなのかね?
※トイレ我慢しながらごちゃごちゃしたスマホ外して、ETC外してとかやってるのかね?
また。
皆が使ってる取り外しやすいスマホホルダーですが、
あれだって完璧じゃない気がしますよ。
走行中にスマホ落としたらただじゃ済みませんよ。
※Aiphoneなんて十万円以上しますしね。
一般的に一番使われていると思われるRAMマウントのスマホホルダーだって完璧じゃないように思えます。
GARMINのハンディGPSにはRAMマウントからそれぞれ専用のホルダーが販売されていてがっつり固定できます。
※大昔のモデルは林道で派手に転倒するとGPSが吹っ飛ぶホルダーもありましたがね(笑)
ツーリング中には、
くらいがわかればワタクシは十分なのです。
※仮に盗まれたとしてもスマホ無くすより、ダメージは少ないしね。
スマホはずっと地図を表示させるものではなく、最悪の事態になった場合の最終防衛線だと思いましょう。
※いざという時に使えなきゃ意味ないってことです。
こんな記事もあります▼
まとめ

何があるかわからんので。
それを楽しめるようになちゃったら勝ちなのですが。
どうやっても不安はあるので出かけちゃえばいいのです。
比較的わかりやすい国道を走りまくって、なし崩しに「バイクで公道を走ることに慣れちゃえ。」というわけです。
というわけで。
初心者のうちは国道メインのツーリングを計画しましょう。
なるべく地図を見ずに。
それがバイクに慣れる早道だと思います。
最初のうちはツーリングルートをしっかり作成ましょう。
紙の地図でざっくりとツーとを決めたら地図は脳内で再生できるくらいまで読み込む、記憶する。
スマホナビのユーザーライダーは圧倒的にルート策定をしないのでほかの人と道の情報を共有できないのよ。
道を間違ったらそこからリカバリをすればいいだけです。
道を間違えるくらいで失敗とかないのです。
失敗は事故にあうとか怪我するとかそういうことなのですよ。
わかりやすい国道であれば、道を外れてもリカバリしやすい。
リルートの練習だと思えば痛痒なしです。
※慌てる小僧はもらい事故、なのでいちいち焦らない。
とにかく。
他かがツーリングですのでイチイチビビる必要はありません。
誰だって最初はあったのです。
そこらへん走って粋がって走ってるにーちゃんや偉そうにしてる中高年ライダーにも最初はあったのです。

Z750D1。
ソロだと好き勝手に止まって写真撮れるのも素敵なのだ。
※同行者がいる場合、ちょくちょく止まると気まずいのだ。
次第にツーリングには何をもっていけばいいか、とかそういう所まで気が回るようになります。
そしたら装備をそろえればよろしい。
最初から何でも用意する必要はないのです。
※ツーリングに持っていくものだって人それぞれでセオリーとか正解なんてないんですよ。
また、最初から長距離を走る必要もありません。
普段の生活上では100kmってすげえ距離だと思いますがバイクに乗ったらそれほどでもありません。
交通状況にもよりますが都市部を含めるとざっくり3時間程度と思っておきましょう。
※慣れと状況によってはどんどん時間が短くなったりするのですが、時間短縮に命を懸けるのはほどほどにしておきましょう。
最初は散歩程度の距離だっていいんですよ。
隣町までちょっと散歩するとかでも構いません。
国道を疲れるまで走って気が向いたら帰って来たっていいのです。
※言わないだけで結構みんなそんな感じで公道デビューしてるはずですよ。
国道の応用として川沿いをずっと走って、飽きたら帰ってくるのもありです。
※川沿いルートはまず迷わないし、標高が低めなので春や秋のちょっと寒い時期でも意外といけるし。
今回はワタクシの同僚が10月末に免許を取ってバイクを買い、めでたく公道デビューになったのでご祝儀的な記事となりました。
長野の11月はかなり寒いのでツーリングデビューとしてはかなり条件悪いんですが、
若いのでツーリング先で凍えて帰ってくるという経験もありだなということで。
中高年には耐えられない寒さも若いと耐えられるんだよねえ。
若いってすげえ。
やっぱり、バイクに乗るにはある程度若さと勢いが必要だと思うのです。
※ある程度阿呆なエピソードがあったほうがバイク乗りっぽいし。
というわけで。
初めてのツーリングに行ってらっしゃい♪
楽しんで帰ってきた暁には惜しみない拍手を送ろう。
※どろどろに疲れたとしても、それも経験なのだよ。
ツーリングの帰りに当倶楽部による余裕があれば、コーヒーくらいは入れてあげよう♪
※要予約。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼