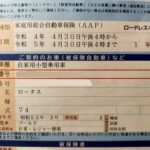里山の紅葉もだいぶ終わりに近いでしょう。
とはいえ。
たまに暖かい小春日和はあるわけで。
そういう日はふらっとバイクで雪をかぶった高山を眺めつつ、
終わりゆく紅葉を楽しみに出かけるのがおススメです。
信州の晩秋の晴れた日は雪山が綺麗

ところが。
長野県には紅葉+αを楽しめるポイントが多いのですよ。
そう、標高の高い山が雪をかぶるのです。
長野県はどこに行ってもどこかしら高い山が見えるもんです。
などなど
この時期はこれらの2000m級の鉱山が真っ先に雪をかぶります。
とはいえ、
回りの低山(スキー場などもこれに当たります)はまだまだ雪がありません。
※里山ではギリギリ紅葉が残ってたりします。
今回はこれらの撮影を狙って長野市から西方面、白馬近辺に行ってみました。
場所によっては紅葉と雪山が一緒に見れらる

かつては、
地元民しか知らなかったようなアルプス眺望ポイントが軒並みメジャーになっています。
改めてネットとかSNSの情報拡散力を思い知ります。
「長野 眺望 穴場」
とかの検索ワードでGoogle先生に聞くと出てくる出てくる(笑)
そしてさらに訪問した人が拡散するので一気に広がっちゃいます。
皆さん、下調べばっちりです。
※勘と経験、地形を読んで探す絶景・・みたいな行き当たりばったりの旅も面白いと思うんですが。

Z1-R。白馬のちょっとした駐車場から。
撮影中、
スナック菓子食いながら歩いている恐らくhakubaに在住してる白人に変な目で見られた。
視点が低いビュースポット
紅葉と雪をかぶった高山を見上げるように眺めるには標高の低い位置をおススメします。
標高が低いとはいえ、
普通に標高(海抜)は東京タワーくらいあるのが長野県です。
長野県内は平らな開けた土地が少ないので自ずとみられるポイントは決まってきます。
そして、
山までなるべく障害物がないポイントと言うのは本当に少ないのですよ。
視点が高いビュースポット
例えば遠い山脈を眺めるために標高の高いところを目指すのも手です。
こちらは高いとことから視界が開けた場所を探します。
山脈に向かって崖状になってる木々の少ない道を選ぶのがポイントです。
大体、日本中どこでも標高高めのビューポイントっていうのは「崖」の上です。
■代表的な例
等は典型的な崖の上です。
※両方ともメチャメチャメジャーになっちゃって晴れた日には人が大量にいます。県外ナンバーばっかりです。
いづれも、
道路から一気に急斜面になっています。
そのため、
木々に邪魔されずに遠くまでを見渡せます。
ということは。
地図を片手に標高差(標高線)をつないで地形を見ていくと眺望のよさそうな個所が特定できるはずです。
※こういう場所を探すのが楽しいのですよ♪

Z750D1。ここは崖っぽい場所です。最近有名になっちゃって混んでる。
誰もいなけりゃコーヒーでも沸かそうかと思っていたのですが。
ちなみに・・
高い視点のビュースポットは場所が特定しやすく、説明も分かりやすいので人が溜まります。
人がたくさん来るようになると、
ワチャワチャしててゆっくり景色を満喫するには多少落ち着きません。
※大抵駐車場も狭いです。

続々やってくる県外のライダーやドライバー。
「ここでコーヒー売ったりして儲けよう!」
という発想にならないのが長野県人。
一方、
低い視点のビュースポットは田んぼの真ん中だったりして、非常に場所の説明がしずらい。
当然、ネットでも「この辺り」ということしかわかりません♪
なので、
隠れた山のビュースポットは意外にも田んぼの真ん中だったりするんですよ。
高山、低山、里山のバランスが大事

わかりやすいのは田んぼの真ん中から見上げる山脈です。
大抵、高山の手前には低山があるのが普通です。
なので、
いきなりドカンと真っ白な高山が目に入るわけではないのです。
ただし、
何となくさまよいつつそういう場所を探すことは可能です。

Z750D1。見事に逆光。でもちょっとカッコいい。
上手い逆光時の写真の撮り方を教えてくれ。
写真に納まる景色の
することは不可能ではありません。
今回はこういうスポットを探して白馬周辺を彷徨ってみました。
個人的には、
大糸線白馬駅の東側の田んぼの真ん中あたりから白馬の山々方面を見るのが好きです。
この周辺は、
山の景色を堪能するにはいいポイントです。
口で説明するのも難しいのですが、この辺ちょろっと走るだけで雄大な山の景色が堪能できますよ。
大抵、いつもほとんど誰もいません。
晴れていれば眺望が最高です。
※できれば午前中の方が西日で逆光にならないのでおススメです。

Z1-R。白馬駅の東側の農道から。
たまたま迷い込んできた、県外ナンバーのアウディのオープンカーと撮影場所の取り合い(笑)
ただし、
みたいな人がごくたまにいます。
雪山からは適度な遠さが大事

当然、いい写真にはなりません。
※それなりにカッコいい写真にはなりますが。
まあ、スマホのカメラで遠くの山脈を写そうと思ったらなかなか難しいもんがありますな。
最大望遠にすると何とか写りますが。
どうやってもスマホカメラではこの雄大な光景感が伝わらんのです。
※勢い、バイク中心の写真になってしまうのですよ。

Z1-R。この影の長さ。これでも14時台ですよ。
携帯カメラでは雄大さが伝わらんな・・
この時期は彷徨ってるうちにどんどん日が傾いてきます。
午後になるとあっという間に影が長引いて光の加減で「秋」を感じることになります。
※14時過ぎでも晩秋の夕方感は半端ないです。
信州の秋は日が短い

※山が高いので日が沈むのが早いのですよ。
撮影したのは14時近かったので既に11月中旬以降はほぼ夕方です。
秋の夕方の西日はまぶしい
晩秋のツーリングで帰路に就く際は「東に向かう」ほうが眩しくないです。
「西日がまぶしすぎてライディング中に視界がなくなる」
という危険な状態を避けられます。
※今回長野市から西に向かったのは帰りに東進したかったからです。
ワタクシは生理的に人一倍目の明順応も暗順応も遅いのですよ。
この時期の朝の東日、夕方の西日は目が痛くなるほど刺激がありますね。
※緑内障ですのであんまり目の神経に刺激を与えたくありません。
こんな記事もあります▼
トンネルが暗いと目が見えない。バイク乗りが明順応暗順応に対応するには? 余計なお世話コメント この記事は、会社のPCでネットサーフィンでサボりつつ、バイクでどっか行きてえなぁと思っているアナタ向けです。 ※ばれないように慎重に盗み見てください。 ... 続きを見る

参考 トンネルが暗いと目が見えない。バイク乗りが明順応暗順応に対応するには?
緑内障が悪化して失明する前に出来るだけバイクも車も乗っておくぜ 人間ドックの眼底検査で判明した緑内障 イヤー参ったよ、緑内障だってさ 症状は全く自覚してはいないですがね 一般には次第に視界が狭まって、視界がなくなるとのこと その期間は、ずーと失明しない人もいるらし ... 続きを見る

参考 緑内障が悪化して失明する前に出来るだけバイクも車も乗っておくぜ
そして、
信州の秋は太陽が沈むと日中小春日和でも一気に冷え込んできます。
日中は汗かくくらいの気温でも日没後は凍えるくらいの温度になります。
の法則です。
※調子に乗ってキャンプすると泣くパターンです。
特に、
風が強めな場合は、一気に気温が下がることがありますので要注意です。
ちなみに・・
この時期のキャンプツーリングをするのであれば、16時にはキャンプサイトに到着しておいた方がいいです。
16時半を過ぎると寒いわ、暗いわいいことありません。
※キャンプ時に慌ててテント設営するのが嫌いです。
夏でもそうですが、
日没の30分前にはキャンプサイトに到着するくらいの時間の余裕が必要ですよ。
日が暮れてから何かするには11月のキャンプ場は寒すぎます。
まあ、
この時期にキャンプする人は少ない・・と思ってたら(笑)
「ゆるキャン△」
の影響で今年はソロキャンパーがいまだに多いそうで。
※相当防寒しないときついっすよ、長野のこの時期のキャンプは。
まとめ

距離を稼ぐには向きませんが道を何度も引き返すようなツーリングには小さいバイクが向いてます。
小さなテーマで集中的に狭いエリアを回るツーリングもいいもんですよ。
大人数ではなかなかできませんので、できればソロで♪
多くても2、3名くらいが限界でしょうねえ・・
※人数が多いと飽きる奴が出てきます。
細い道をUターン覚悟でガンガン突き進んで誰も知らない絶景ポイントを探すのはかなり楽しいバイクの遊び方の一つです。
そういう場所では、
方向転換が絶対的に楽な小さいバイクが気楽です。

Z1-R。この後、Uターンする。
嫁のZ750D1もワタクシがUターンする。
奴がZ750D1を田んぼに落っことして引き上げられないよりはマシだ。
最近はやりの「アドベンチャーバイク」は250ccでも高速走行の安定性をねらってか車格がでかいです。
ワタクシとしては、250ccクラス以下のオフロードバイクをおススメします。
※オフロードバイクはあぜ道や河原に突っ込んでいけるので撮影スポットの範囲が広がります。
それに写真を撮るなら、
方向的に「逆光になる時間は考えたほうがいい」ですね・・
そこまで考えてませんでした・・
※相変わらず思慮が浅い。
実は、帰りの東進時の光の方向は計算してました。
現地について、
「被写体が逆光・・だと!」
と思っても遅いのです。
相変わらず、浅はかですなぁ♪
一つ勉強になったので別に後悔はしていません♪
※また行けばいいんですよ♪

Z1-R。こういう状況でも狙って格好よく撮影できるようになりたいもんです。
自分ではいいと思ってたんですが(笑)
スマホのカメラモードの使い方もいまいちわかってない。
例年、長野県では12月入ると
という長い冬がやってきます。
それまでになるべくジタバタしておくのが
「バイクを冬眠させる前の長野のバイク乗りの習性」
なのです。