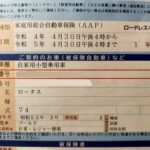ガエルネのミドルカットの紐革靴です。
バイクのブーツ事情というのを振り返って記事を書いて見ました。
たかがバイク用のブーツでもトレンドがあるんですな。
昔はみんな長靴みたいなレース用ブーツを履いてたというのに。
昔はみんなレース用ブーツを履いてた

最近はブーツというよりシューズですな。
思えばブーツ一つをとっても30年以上に間にはいろいろな流行や変化があったんですよねえ。
それこそ昔はみんな適当なスニーカーみたいな靴でバイクに乗ってたような気がします。
スニーカーだとシフトペダルのところが黒くなるし、その箇所が痛んで穴空いたりするのですが。
スニーカーのシフトペダルにあたるところに巻くベルト状のアイテムがあったけれど歩きにくいし、ずれるし、シフトフィールが悪くなるので不人気でしたな。
※ワタクシは当時から「どうせ消耗品なんだし、高いスニーカーは買うもんじゃない。」と思っています。
とはいえ、
今も昔もライダーの靴における選択肢はそれほど多くないのでした。
※教習所でバイクに乗る時の靴についてはどう指導してるんだか知りませんが。紐靴はいいとか悪いとかあやふやだし。
ワタクシがバイクに興味をもった当時のスニーカー以外のライディングブーツといえば「レース用。」でした。
膝の少し下まである革製のやつです。
※ファスナー付きの長靴みたいなやつです。
今のレーシングブーツはゴテゴテしていますが当時のレーシングブーツは、
高級品だけはつま先にバンクセンサーがついてるくらいであといたってシンプルなものでした。
※脛当てとかもついてない。
そして。
基本的に革ツナギと合わせて使うので派手なカラーリングのブーツも多かったのです。
このカラーリングは絶望的に普段着に合いませんが、多くのライダーは街乗りでカラフルなレーシングカラーのブーツを履いてました。
今思えば当時は公道で革ツナギを着てバイクに乗ってる人はたくさんいたのですが、
貧乏人には革ツナギは高根の花でした。
※信じられないかもしれませんが20代前半のライダーは無理して借金して革ツナギを買ってたのです。
貧乏なライダーでも高価なツナギは買えなくてもレーシングブーツなら買えたわけですよ。
※当時の上野のバイク街で 安っぽい革を使った無名メーカー品の レーシングブーツなら1万円くらいから買えたのです。
この 安っぽい レーシングブーツを街中で履いてるライダーをよく見たものです。
※貧乏人の普段着であるジーパン。この裾はブーツにイン派とアウト派がいたな(笑)
今思うと猛烈にダサいけれど当時のライダーはこれが普通でした。
そのまま大学の授業に出てたりした同期も結構いたし、
バイクがレプリカ中心だった時代なら、まあそうなるだろうというアイテムのチョイスだったわけです。
今は革ツナギでツーリングしてる人なんてほぼ見ませんな。
レーシングブーツを履いてツーリングしてる人もほとんど見ません。
我々のようなあの時代を知ってる年代のライダーはみんなそういう経験をしてるはずですな。
ワタクシも革製のレーシングブーツは持ってたしねえ。
※さすがに大学には履いていかなかったけれど。
そういう時代だったのでしょうねえ。
今思えば蛍光カラーで肩が張ってるスキーウェアみたいなもんですかね。
※こんな流行り廃りも一回転するんですかね?(笑)
ちなみに・・
ブーツの話ではありませんがレプリカバイクにデザインが統一された革ツナギ+ブーツ+グローブというのはレプリカ小僧どものあこがれのスタイルでした。
※ものすごくお金がかかる。上野のバイク街でも高価な革ツナギ屋さんがたくさんあったのです。
上下セパレート式の革ツナギは一体式に比べると 主にトイレで 使い勝手が非常にいいのですが、
ワタクシの周りではダサいと言われていました。
次第に革のツナギは廃れていくのですが、
その革パンと呼ばれた革ツナギの下半身だけバージョンがその後しばらく生き続けます。
大抵黒一色で膝と腰にパッドが入ってる感じです。
※膝のバンクセンサーはあったりなかったり。
これならレプリカバイクに乗らなくてもそれなりに様になるのです。
ワタクシも上半身はジャケットで革パン+レーシングブーツというスタイルで日本中を回りましたし。
今では革パンを見かける機会がだいぶ減りました。
BMWモトラッドのイベントでは BMW純正の革パンはめちゃめちゃ高いんですが 結構革パン率が高いように見えました。
高齢ライダーの間では今でも普通に装備されるアイテムなのかもしれません。
確かにコケて路面を滑っていく場合、ジーパンの何倍もプロテクション能力は高いと思いますが、
その手の高価な装備は今の若者にはウケないのかもしれません。

今はすっきりしたタイプも多いけれど昔はアメリカン乗り用だった気がします。
やっぱスポーツバイクは膝カップが入らんとねえ。
リンクからいろんな革パンが検索できるようになっています。
編み上げ革靴とエンジニアブーツの時代

この頃はレプリカはダサいという風潮も出てきてちょっと前まで高価に取引されてたレプリカバイクの値段が暴落します。
そうなると必然的にレース用のブーツはダサいということになっていくのです。
ではその代替はなんだったのか?
ゼファーから始まったNotレプリカである普通のバイクには革ツナギは似合わないんですよ。
普段着っぽい服装で普通のバイクに乗る人が増えるたのです。
普段着でバイクに乗るということは、レーシングブーツを履く人がどんどん減るということです。
ではレース用ブーツの代替はなんだったのかって話です。
ライダーは再び普段履きの靴でバイクに乗ったのですが、やっぱりスニーカーだとシフトペダルのところが痛むのです。
で。
ホーキンスに代表されるような編み上げのミドルカットの革靴がライダーの間で流行り始めます。
この頃、バイク用品店でもレーシングブーツの代わりにミドルカットの革靴が増え始めました。
革靴でもやっぱりシフトペダルが当たる箇所は痛むのですが、
スニーカーの化学繊維より革の耐久性ははるかに高いのでまあ良しというわけです。
ただし。
革の編み上げ靴は脱ぎ履きが非常に面倒くさい。
ツーリング中は靴を脱いで小上がりに上がるタイプのお店では昼食をとらなくなるのです。
これと同じころ。
某TVドラマで「キムタク。」で有名な木村さんがバイクに乗ったわけです。
この時履いてたのが革製のミドルカットのエンジニアブーツと呼ばれるものでした。
それまでエンジニアブーツの存在を知らなかった人たちまで履き始めます。
これがまためちゃめちゃ流行ります。
ワタクシもホーキンスのエンジニアブーツを高円寺の靴屋で買った記憶があります。
※当時、15000円くらいした。
エンジニアブーツとは要するに安全靴です。
つま先に金属製のガードが入ってるので革が伸びないため、足の形が合わないとつま先がちょっと痛い。
金属製のガードは冬は猛烈に冷たくなるのでつま先から冷える。
当時のエンジニアブーツは決して使い勝手はよくありませんでした。
今でもエンジニアブーツはおしゃれ靴の一種として人気がありますが、
軽くて冷たくない樹脂製のつま先ガードになるのはだいぶあとのことです。
エンジニアブーツは紐靴ではないので紐の煩わしさはないのですが、
靴の形状からやっぱり脱ぎ履きは座らないとできなかったです。
これらはレーシングブーツとは違って一応市民権がある靴なので、
ツーリング先でも 靴レベルでは 浮くことがないため、気まずくはありません。
こういうライディングシューズのチョイスはアリです。
ただし。
革靴は雨にとても弱いです。
雨天ツーリング後に放っておくとほぼ間違いなくカビますし、
濡れた後はすぐにしっかり乾燥させてミンクオイル等でケアしないと革がひび割れて裂けるなんてこともありました。
※エンジニアブーツは開口部が広いので雨降ると靴の中に水がたまるし。
まあ逆にこれだけやっておけば いい革なら かなり長持ちします。
現にワタクシの20年以上使っている革製ミドルカットの編み上げブーツは未だに現役です。
多少、シフトペダルが当たる位置が痛み始めましたが恐らく10万キロ以上これで走っています。
キックのオフ車にもこれで乗ることがあるので靴裏はちょっと傷んでいますが、
下手すりゃ東京在住の頃から同じ靴を履いてるかもしれないのでコスパ的には素晴らしく良いです。

少なくとも20年履いてるホーキンスのハイカット革ブーツ。
この靴は一番革の素材が良かった時代のホーキンス製です。
さすがにシフトペダル部分は痛み始めていますが雨天後は確実にメンテしてきたので今でも不通に履けます。
有名メーカー品でも時代とともにコストダウンしたりするので、
全部が良質であるとは言えないということをワタクシはホーキンスに教えてもらいました。
靴は特に同じメーカーの同じ型番でも明らかに作りがちゃちくなってることは多いです。
※革靴ではないけれど街歩き用の靴であるメ〇ル。最近のものは高価格なくせに作りがひどく安っぽくて寿命が超短いのは残念です。
最近のライディングブーツ

ワイヤーフィット式とかオフロードブーツのショート版でオンロード用みたいなのもありますね。
ライディングブーツは今も進化しています。
最近のスニーカー系のライディングシューズは、
ダイヤルでワイヤーを引っ張ってワンタッチでフィットさせるタイプが増えましたな。
確かにこれなら脱ぎ履きの手間が最小でフィット感がよさそうです。
やっぱ紐靴は面倒くさいのよ、かっこいいけど。
それに。
痛みやすい箇所であるシフトペダルの当たる位置にはしっかり補強が入っています。
この補強、左側だけにあると機能性がある靴として仕入時だか販売時だかの税率みたいなものが変わるそうです。
左右に補強があれば「デザイン。」として押し切れるんだとか。
※ライディングシューズ屋さんに聞いたので多分本当。
スニーカー系のライディングシューズは高機能で軽くてメンテもいらず、通気性もよいといいことづくめ。
ですが高機能な分、革靴並みにいい値段しますな。

最近は街歩き用のシューズもワイヤーフィットものが多いよね。
ダイヤルロックともいうらしい。
脱ぎ履きは楽そうだしフィット感は良さそうだけど持ってないや。
リンクからいろんなワイヤーフィットのライディングシューズが検索できるようになっています。
最近のブーツで目を引くのはオフロード用のブーツをローカットにしたようなやつ。
オフブーツのようにバックルで足を固定する仕組みです。
安全性は高そうですが、この方式だとどうしても靴全体が厚みを増すのでシフトペダルの位置調整はしたほうがよさそうです。
※某有名ツーリング用地図の編集してるRちゃんの靴がそれだった気が。 金持ちは違うな。

バックル式とでもいうんですかね。
このカテゴリも最近増えてきたねえ。
靴部分もスニーカーっぽい商品もありますね。
リンクからいろんなバックル式のライディングシューズが検索できるようになっています。
そうそう。
最近の革製ミドルカット紐靴は、
「内側サイド部にファスナーがついててイチイチ紐を緩めなくても靴が履ける。」
という手法に進化しましたな。
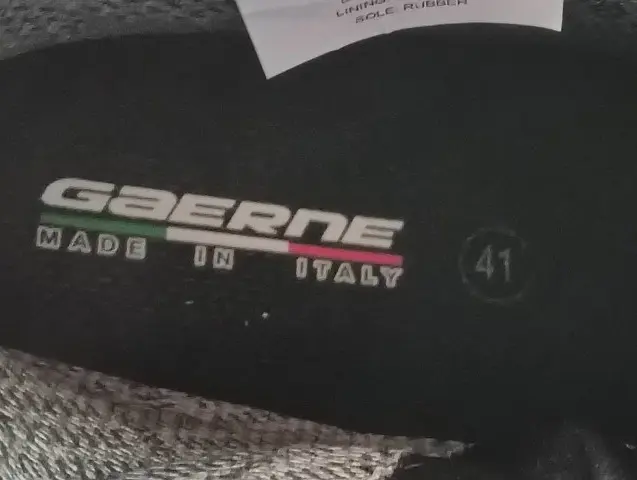
今どき珍しいイタリア製。
一流オフロードブーツメーカー、ガエルネのイタリア製造もんです。

ワタクシが今回買ったのはこのタイプ。
やっぱ革靴がいいのよ、ワタクシは。
オフブーツでお世話になってるガエルネだし。
つくりもしっかりしてるし買ってよかった♪
靴底がビブラムソールかそれと同レベルのものがいい。
キャンプ場などの不整地でバイクを押すこともあるからね。
ライディングブーツでの街歩きを考える

まあそれを購入対象から除外したのはツーリング先の街歩き時に浮くからです。
ライディングシューズはライディング時を重視するのももちろんアリです。
レースやスポーツライディングを追求するならベストフィットで細かい動きにも対応できるものを求めるべきです。
また安全性を重視するのももちろんアリです。
くるぶしまでしっかりプロテクタが入ってるものやつま先に補強が入ってるものを選ぶのも大いにアリです。
軽快性を求めるのももちろんアリです。
軽くて安いスニーカーを短いサイクルで履きつぶすというスタイルもアリです。
濡れても乾きやすいしメンテは不要で脱ぎ履きもしやすい。
見た目重視ももちろんアリです。
機能性よりおしゃれさを優先したデザインのライディングブーツもたくさんあります。
最近はバイクは自分を引き立たせるアイテムとしての役割も大きいようなのでこういうのもアリなんですよ。
※バイク用の革パンだって今の主流はストレートっぽい奴ですし。
まあライディングブーツなてのは何でもいいんですよ、
法的な規制はないんですし自分が使いやすくて納得していれば。
レプリカ時代のようなセオリーなんてものはないし、今の時代好き勝手に多様性を追求してもいいのです。
ただし。
食事や温泉でブーツを履きなおすシュチュエーションというのは多分にあるのです。
人によっていろいろな価値観や選定基準はあると思うのですが、
ワタクシは上記のような観点でライディングブーツを選んでいます。
※ブーツに限らず、ライディングギアは全部そうです。
ワタクシも最近はツーリング先でバイクを降りて 少しは 街歩きしたりします。
※20代のワタクシなら街歩きなんて絶対やりませんでしたが歳を取るとはこういうことなのですな。
バイク乗りってバイクを降りて観光地を散策してても一瞬でバイク乗りとわかっちゃうじゃん?
そういうのを極力減らしたいわけですよ。
※でもタンクバッグを肩から下げて帽子かぶってライディングジャケット着てるのでやっぱりばれるんですが。
最近のワタクシはそういう状況であんまり浮かない格好を選びがちです。
※そしてそういうところに行く場合はZ1-Rだと目立ちすぎるのでVTとかDTとかで行きがち。
ちなみに・・
昨年末に東京&千葉に行ったのですがその時見かけたライダーがダウンジャケットしててびっくりしました。
ダウンジャケットなんて風に弱そうなものを着て走るなんてワタクシには信じられませんでしたがこれも時代なんでしょうねえ。
※しかも結構な前傾姿勢のスポーツバイクでですよ?
ダウンジャケットは汚れると大変だよ。
風圧で破けることとかないのかしら。
マフラーやエンジンに触れれば熱で溶けそうだし。
ちゃんと温かいダウンジャケットは結構高いし。
普段着でバイクに乗ることにここまで抵抗がなくなったということなのでしょう。
バイクに乗るのに専用のウェアとか馬鹿じゃねえの?って話ですな。
確かにバイク専用のウェアはおもちゃ的なギミックが満載で安っぽいわりに値段が高い気がします。
※妙に目立つしねえ。
それにしても真冬にバイクに乗れる関東地方はうらやましいですな。
革製ブーツの手入れ

革製品はこれを最初にやるのとやらないのでは持ちが違うんですよ。
革のブーツの初期化は新品の革グローブを下したときにやることとほぼ変わりません。
こんな記事もあります▼
最近の革製品は表面のなめしが固いのが主流なので昔ほど新品時の手入れは必要ないのかもしれませんが、
革細工を趣味にするものとして使い始める前にしっかり初期化をしておきたいのです。
昔は表面を固くなめされた革製品は安物が多かったのですが。
今もそうだけれど柔らかいなめし革の靴はほぼ見なくなりましたねえ
表面が固くてつるつるして光沢があるような加工をした革は加工しやすいのですが、
革自体が伸びないし弾性があんまりないため、革自体が裂けやすいのです。
これは最近の革製品の特長ですので仕方がありません。
※ワタクシが趣味の革細工をする場合は柔らかく油が浸透するような革素材を使うことが多いです。
革靴の初期化

ガエルネのブーツ。
革靴から紐を取り除きます。
で。

ミンクオイル。
いつもネットで買ってたけれど近所の靴屋で普通に売ってた。
しかも安いと来た(´;ω;`)
ミンクオイルを適当な布で多めに刷り込む。
※この時、オイルが浸透せずに伸びが非常にいいのが表面のなめし加工が固いやつです。

ファスナーのギミック。
こういう入り組んでるところは念入りに塗り込みます。
ファスナー開閉部付近にミンクオイルを徹底的に塗り込みます。
で。
30分から1時間ほどおいてなじませたら、
乾いた布で余分なオイルをふき取ります。
※オイル分が多いと余計な埃を吸って乾燥が加速するのだ。
そのあと、紐を通します。

ガエルネのブーツ。
この編み上げ方、誰もやってないので気に入っています。
※誰も気が付かないんですが。
紐は長めなことが多いので、それなりの通し方で多少距離を稼ぐことで蝶結びを小さくできますよ。
※元靴屋の店員のYさんに聞いた手法です。
今回買ったガエルネはほぼオイルが浸透しない固い革ですなぁ。
オイルを塗ってもさほど柔らかくはなりませんので注意して使わないと表面が傷む前にいきなり裂けるかもしれません。
で。
初期化が終わった後、試し履きでVT250FHを引っ張り出して30kmほど走りこんできましたが、まだまだ長野の風は超寒いのでした。
※梅は多少咲いてたけれど杏も桜も全然咲いてないし、この日の夜は雪が舞いました。
まとめ

ツーリングがまた楽しみになりました♪
ワタクシはたいていバイクに乗る時のブーツを2足用意していて交互に運用しています。
一個だけ徹底的に使い倒すと長持ちしないからです。
昨年秋に10年間直し直し使ってたモト〇ァンゴの革製ミドルカット編み上げブーツの底が全面的に剥がれたので廃棄になりました。
※それでもゴリラグルーで何度も直したんですがいよいよ限界。最近の革靴の底部は接着式が多いのではがれやすいです。
2025年のバイクシーズンを迎えるにあたり、ようやくガエルネのブーツを入手したのでした。
そう考えるとホーキンスの革靴は長持ちですなぁ。
都合20年使っていますがその間に買ったいくつもの革靴を見送っていまだに現役です。
※当時、値段的にそんなに高くなかったんだけれどね。
いい革ブーツは一生もん、みたいなことを師匠のI氏が良く言ってましたが本当にその通りですねえ。

ホーキンスのブーツ。
このホーキンスくらい長持ちしてくれればいいんですがね・・。
今回買ったガエルネはどれくらい持ちますかねえ(笑)
林道ツーリングではオフロードブーツをはくとして、それ以外のツーリングでは普通に使うからねえ。
街も歩くし。
ガエルネは最近のブーツなので革が固い気がしますが、
新しいブーツはやっぱり気分がいいのです。
※新しい分、使い倒した革の渋い風合いは全くないんですがね。
ちなみに・・
実はワタクシは身長のわりに足のサイズが小さい26.0cm(ものによっては25.5cmでもOK)のです。
※メーカーによっては26.5を選ぶこともありますが。
最近はみんな足のサイズがでかいのですなぁ。
※甥っ子とかに余裕で負ける。みんななんでそんなに足がでかいの?
スポーツ用品店などではそのくらいのサイズの靴は不人気でたいてい売れ残っているのです。
というわけで。
ワタクシが普段使いの靴を買う場合、シューズショップやスポーツショップの 売れ残り お買い得品の中から買ったりします。
ウォーキング用のシューズとか全部それです(笑)
まあワタクシは 軍隊で訓練されたので 歩き方が上手いらしく、
たくさん歩いても靴底が全然減らないので靴の買い替えサイクルが長いのですが。
※異常なまでに靴底が減らない。靴は買うと高いので少しでも長持ちさせるのが節約になるのです。