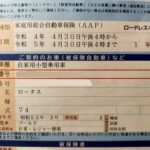その一つがHONDAのセミエアフォークです。
ワタクシもなんだかよくわかってません。
ただし、既定の圧力にしたらいい方向にわかりやすい変化があったのです。
80年代の過渡期のバイクには謎がいっぱい

もしかしたらずっと過渡期なのかもしれませんが。
80年代のバイクにはいろんな過渡期の装備が搭載されているのです。
当ブログでは何度も振り返りますが80年代のバイクの進化はすさまじいものでしたな。
少なくとも今の10倍以上のスピードで進化してたように思えます。
この時期はいろんな機構が実験的にレースに導入されてたのです。
バブルで人口も増えててバイクメーカーには勢いがありました。
新機構はレースでちょっと実験した後、1年くらい遅れて市販車に実装されたりしたのです。
※ろくに煮詰めてない気もするけれど当時はそれが普通でした。
とりあえず、
現時点を到達点としてバイクのいろんな部分は、
進化の過程でいろんな試行錯誤がなされてきたのは事実なのです。
例えば、
などなど、この時期に進化した項目はたくさんあります。
※油圧クラッチとかもそう。HONDAのインボードディスクもそう。
ただし。
現在までその流れが続いているものはそんなに多くはありません。
あくまでも過渡期の実験的な機構も多く、
気化器の電子制御化でアナログ式の制御機構が消えていっただけでなく、
加工技術の進化や進化の方向性の見直しによって刷新されたり、淘汰されたりして、
今でも残ってる機構はそんなに多くないのです。
今は余計なことしなくてもシンプルな機構で対応できるようになったりもしています。
※コストダウン的な意味合いも大きいけど。
当時は1年単位で速やかかつ大量に試行錯誤が繰り返され、
モデルチェンジどころかマイナーチェンジごとに新機構の投入が行われたすさまじい時代だったのです。
現在に至るまでいろいろあったんですよねえ。
中でもフロントフォークのシステムは一時期進化の方向が迷走した感があるのです。
フロントフォークいろいろ

中高年のライダーにはどれもひたすら懐かしいのではなかろうか。
似たような機構でもメーカー毎に呼び名が違ったりしたのです。
「A.N.D.F。」
これを略さずにいえる人はおぢさんですな。
AntiNoseDiveFork(アンチノーズダイブフォーク)の略です。
キャリパーからフロントフォークのボトムケースにつながるホースがありましたな。
※ワタクシもGSX1100Sで経験しました。メッシュホースにする時にバンジョー部が多く割高になったので嫌いでした。

GSX1100S。素晴らしくカッコはいい。
カタナはA.N.D.F付です。
「P.D.F。」
といってもAdobeのファイル形式じゃありませんよ。
PositiveDumpingFolk(ポジティブダンピングフォーク)の略です。
※ワタクシもGSX-R1100で経験しました。当時はいったん設定したらいじることなかったのですが今ならいじりまくりそうです。

GSX750S3。
3型カタナにはP.D.Fが装備されていますね。
今どうしてっていうくらい高価格で取引されてるのが不思議。
50万円くらいなら欲しいと思ってたけれど、まともな個体はその倍くらいするね。
いずれもブレーキ時の姿勢が前のめりになるのを防ぐという機構なのですが、
フロントが突っ張ってそのまま滑っちゃいそうで怖い感じもありました。
※なので、この手の機構自体をキャンセルする人が続出したんですけどね。
名称こそ各社違っても似たようなシステムを各社がレースで実験して、
それぞれ工夫を凝らしたシステムを公道用の市販車に搭載してたのです。
当時はそんなの公道レベルで必要なのか?と思うような トンデモ 機構ですが普通に採用されてたのです。
※今思えば、無駄に贅沢ですな。
その中でHONDAがこだわってたのがセミエアフォークというシステムです。
ちなみに・・
流行りの豪華装備と言える倒立フロントフォークの登場はかなり後の話です。
最初はオフ車に採用されたような記憶があります。
※失念。興味があれば自分で調べて。
見た目がごつくていかにも強力そうなので、オンロードバイクでも後期のレプリカ勢にはこぞって採用されました。
ただし。
ので、運動性が高い高価なレプリカに近いスポーツバイクにのみ採用された感じです。
※マジで素人が公道で使うなら普通のフロントフォークと何ら変わりません。取り回しが悪くなるだけです。
同時期の似たような排気量の車重の倒立フォークと普通のフォークを持って比べればわかりますが、
普通のフロントフォークのほうが軽いです。
※はっきり重さと太さの違いが分かります。
軽量な普通のフロントフォークのほうが運動性が高いと思うのですが、
やはり使い勝手うんぬんより、見た目の迫力のほうがバイクのセールスポイントとして強いのは間違いないようです。
ゆえに。
当時は猫も杓子も「倒立フォークが偉い。」という風潮でした。
※旧車のカスタムバイクにもこぞって倒立フォークが付けられてたもんです。
そんな風潮だったので、
最強原チャリのKDX125SRにも倒立フォークが採用されたりもしたのです。

KDX125SR。鉄製のフォークには磁石入りのトレーが張り付く。
まあそれなりにカッコはイイんですがね。
ただし。
KDX125SRの倒立フォークはコストの関係でアウターが安い鉄なのでくそ重いのです。
DT200WRのアウターがアルミの倒立フォークと比較すると重さの差は歴然です。
※軽金属とはよく言ったもんだ。
さらに。
コスト削減のため、ダンパー機構が片方にしか入ってないというテイタラク。
※でも激しくコースを走らなきゃこれでも十分な気もします。ライダーの体重にもよるしね。
このように商品力を高めるため、運動性能を無視した格好だけの倒立フォークもあったのですよ。
何でもかんでも見た目の迫力がありゃいいってもんではないんですよ。
セミエアサスとはなんだ?

これから本文はようやく本題に入ります。
じゃあ、セミエア式フロントフォークってのはなんだって話です。
文献による解説
フロントフォークのインナーチューブ内に大気圧より高い圧力を加えて、
乗り心地と操縦安定性の両方を向上しようという試みの産物です。
フロントフォークがストロークしてインナーチューブ内の空気室容積が減少すると空気が圧縮されます。
この時、圧縮された空気は「空気バネ。」になるので圧縮度合いに伴い、反発力が二次曲線的に大きくなります。
空気バネに対して金属スプリングのばね定数は一定なため、ストロークが大きくなると空気ばねの影響度が高まります。
という仕組みらしい。
ワタクシの理解
普通のフロントフォークの内部に空気の層を作って予め加圧しておくことで、
フォークのダンピング特性をオイルとスプリングだけより細かく設定可能になる。
ココまでは文献をほぼ踏襲しています。
確かにセミエアフォークをばらすと上部には長めのカラーというかスペーサーが入っていて、
「空気バネのための容積を確保してるんだね♪」
みたいな雰囲気はありますが。
※セミエアフォークでなくてもフォークの上部にカラーが入ってるのは割と普通ですが。
なので。
空気を加圧しない状態であれば普通のフロントフォークと何ら変わりない動きをする・・ハズ。
むしろ加圧しない方がサスが無駄に突っ張らないので段差を超えたときの衝撃は少なくなる・・。
というのがワタクシの小さい脳みそでの理解です。
これを踏まえたうえで。
VT250FHの35年以上前のセミエアフォークの性能なんかどうでもいいので、
フォーク内部の空気は大気圧にしていろんな調整をするという方針を取っていました。
※わざわざフォークトップのエアバルブから空気を輩出してました。
海のモノとも山のモノともわからん機構なら、
全部の機構を捨てて自然な動きのほうがよかろうということで。
でも。
走行性能はまあまあなのですが、
どうやっても不具合が消えないのです。
以前も記事で書いた段差を超えるときにステム周りに衝撃がくるのがストレスなのですよ。
※衝撃を受けるたびに寿命が1日減っていくような気がします。なんだか壊れそうでねえ。
それでもいろいろジタバタしたのです。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼
ちなみに・・
「バリ伝。」で人気のCB-Fにもセミエアフォークが入っていますな。
※CBX(1000cc6気筒)にも入ってるそうな。
ご丁寧に左右のフォークを連結させて空気圧の偏りをなくすという凝ったものでした。
※GPz-F系もそうなんだってね?知らなかった。
とはいえ。
セミエアフォークは当時から、
等の理由で、
「理想は高いけれど素人には手に負えない。」
という代物だったみたいです。
なのですが。
80年代中盤くらいまでの多くのHONDAのスポーツ系のバイクにはセミエアフォーク搭載されたのです。
※Kawasakiは何時から何時までなんだろね?
ワタクシの理解を超えてるセミエアフォークの挙動

試行錯誤した結果、ステムベアリングを交換して衝撃を半分以下に抑えることができました。
でも完全に衝撃が消えたわけではありませんでした。
これが気に入らない。
衝撃解消のために、
で、最初よりはかなり衝撃がなくなった当倶楽部のレストアVT250FHです。
が。
天下の世界一のバイクメーカーであるHONDAのバイクなのに、
走行中に少しでも衝撃が来るのは異常だと思うんですよ。
ワタクシは納得していませんよ。
ステムナットの締め直しは二度くらいやりました。
フックレンチはすでに持ってたけれど閉めこみやすい形状のものを追加で買ったりもしました。
※ゆえに当倶楽部のガレージにはフックレンチが現在3本あります。
ある程度まで衝撃は減ったのですがそこから何をやっても一向に良くならないのです。
CBR250Rと同じフォークを無理やりVT250FHに搭載したのでフォークが固いのか?という結論に達しそうになっていました。
※盲目的にそれしか考えられなくなってたんですわ。こういうのが一番迷走するパターンです。
が。
何度目かのステムナットの締め直しの確認の後、
なんとなくセミエアフォークに加圧してみようと思い立ちました。
今まではセミエアサスは無加圧の大気圧のままのほうがいいという確信があったため、無加圧でした。

VT250FHのフォークにエアを加圧する。
一回のストロークでどんだけ入るんだか知りません。
たまたま持ってた自転車用の携帯用のちゃっちいハンディポンプ(もちろんエアゲージなんてない)が、
セミエアサスのエアバルブに適合したのでこれを使うことにします。
コレでシュコシュコと加圧してみました。
VT250FHのマニュアルによると、圧力は0.0から0.4kg/cm2となっています。
※0.0ということは大気圧でもいい、ということですよね?違う?
大した圧でもないけれど、一応ポンプのストローク数を左右で合わせてみました。
※ポンプのアダプタを外す際、ちょっとエアが漏れるので厳密に合わせることもできず、超適当です。

VT250FHのフロントフォークトップ。
フォークトップのエアバルブにはキャップが付いています。
ですが。
軽く試走して段差を超えてみたところ・・。
明かに体感できるレベルで衝撃が減ったのですよ。
なんだこれは?
ステム周りに来てた衝撃が半分以下になりました。
もしかして2年以上悩んだ結果がコレ?
お金も時間も手間もかけたのに?
空気いれただけ?
まあ、いい。
こういうのは感覚の問題なので、共感を得ずらいのです。
この手の感覚的なチューニング系の話はネタがたくさんあるのだけれど非常に文章にしずらいのだ。
※皆の者、心眼を使ってワタクシの言いたいことを読み取るのだぞ。
ちなみに・・
上記もしていますがHONDAのセミエアフォークは正確に空気圧を合わせるのが大変です。
加圧した後、エアバルブからを空気入れのアダプターを抜くときに必ずエアが漏れるからです。
0.4kg/cm2という低圧なのでちょっと抜けただけでもだいぶ狂うはずです。
同じ理由で空気圧チェックのため、エアゲージを当てれば必ずエアが漏れるので適正値にセットするのも難しいです。
再計測するたびに値が変わります。
当面は自転車用の携帯空気入れを持参して、
出先でちょこちょこ空気を入れワタクシがいいと思うポンピング回数を模索するつもりです。
みんなセミエアフォークの加圧はどうやってるんですかねえ。
そうそう。
セミエアサスにはコンプレッサーで一気に空気を入れてはいけないらしい。
急にフォーク内の内圧が上がって車体が起きてバイクがコケるリスクが伴うみたい。
※センスタでやればいいじゃんね。
また、
加圧しすぎると空気漏れ止め用のシールが抜けちゃうこともあるとのこと。
まあ、
フォークトップについてるエアバルブは短いため、
当倶楽部にあるエアコンプレッサーだと物理的に接続できないんですが。

VT250FHのフロントフォークトップのエアバルブ。
専用の空気入れでもあったのかしら?
多少多めに加圧しておいて、
アダプター外す時に多少抜けてもダイジョブ♪
というくらいがちょうどいいような気もしますがコレも数値化しづらい。
結局、自己満足の自己責任ってやつですね。
まとめ

ステムの締めつけでもかなり良くなったとはいえ、
今回セミエアサスの空気圧を調整すればもっと良くなる確証を持ったワタクシがいるのだ。
原理はわからないけれど、セミエアフォークに加圧するだけでステム周りに来る衝撃が解消されるなら安いもんです。
VT250FHのステムの締め付けは結構めんどくさいのよ。
ハンドルやトップブリッジを外すのはともかく、
カウルもヒューズボックスもハズさにゃならんし。
※お隣の猫は作業の邪魔しに来るし。
セミエアの加圧で段差を超える際にステム周りに来る衝撃が解決すれば安いもんです。
とりあえず、
現状で200kmほど走りこんでみた結果、
衝撃は100%消えたわけではないのですがかなりいい感触です。
※忘れたころに段差を超えて衝撃が来ることがあるけれど、ほとんど解消したといってもいいレベルになっています。

戸隠の鏡池。
ここまでエアフォークの感触を試しに散歩としゃれこんだのだ。
今後、セミエアフォークに加圧して数値を計測しつつ、もう少し走りこんでみようと思います。
もっと早く気が付けばよかった。
とはいえ。
確かに、セミエアフォークに加圧すると加圧する前に比べてフロントが多少ふわふわする感じになります。
これを嫌った先人たちがセミエアフォークのシステムを殺す方向にセッティングしたんでしょうねえ。
でも多分、フォークの空気圧を大気開放しちゃうだけだと段差を超えるときにガツンと衝撃が来たはずです。
ネットの情報には、
セミエアシステムを殺したという記録はあるけれど、その反作用的な文献は残ってないんですよねえ。
フロントフォークが多少フワフワしてても 割と速めのペースで 巡行するのに何の不安もありませんよ。
がんがん攻めて走るわけではないので、多少ふわふわしてもガツンと言う衝撃がないほうが優先です♪
いろいろ言われるセミエアフォークですが、
公道で一般人が普通の速度で走り回るレベルなら全然問題ないと思います。
それでも現在の技術であればセミエアに頼らなくても、
という理想のセッティングにできるんでしょうねえ。
まあ35年前の古いバイクです。
出来が悪くて当然、むしろ現在普通にツーリングに使えて走れるだけでも感心に値します。
※普通ならとっくに廃車になっててもおかしくないです。
レースするわけでもないし、誰かと競うわけでもありません。
当時の機能なりに楽しめばいいのです。
こういうのを面白がりつつ、ゆっくり細部を詰めていく所存です。
幸い、セミエアに加圧すると多少良くなると言うヒントを得たので幸先は明るいです。
※今回のように、ちょっとした気づきまで数か月とか数年かかることもあるけれど、これを攻略するのが面白いのよ。
もう一回書くけれど、
こういうのは個人の感覚的な要素が大きいし、人によって許容範囲はそれぞれです。
所詮個人の趣味なのでワタクシがいいと思うようにやっています。
そうせセオリーなんてないんだから。
そうそう。
セミエアフォークに加圧しても空気は勝手に抜けるのが当たり前みたいです。
ツーリング前には毎回加圧し直した方がよさそうです。
セミエアフォークは、空気圧の調整頻度が高く、めんどくさかったから廃れた技術なのかもしれません。
とりあえず、
この手のチューニングは走りながら調整しながらデータ取るのが手っ取り早い。
理想の空気圧を求めてエアゲージとエアポンプ持って久々にデータ取るための遠出するしかありませんな。
※っつっても下道で400kmくらい一気に走る日帰りツーリングなんですけどね。
こんな記事もあります▼