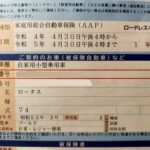いつの時代でもその時点のカウルは最先端のデザイントレンドと性能を誇っていたわけですが、
もしかしたら数年後はあの時代のカウルはダサいとか言わたりするかもしれませんし、逆もあるかも知れません。
流行なんてそんなもんですよ。
今更ながらカウルとは何か?

このカバーがカウルです。
前面だけでなく、横や後ろ部分の覆いも広義ではカウルです。
でもカウルというとバイクの全面にある覆いのことを指すことが多いです。
当ブログでも何度かカウルの有用性について書いたことがあります。
意外と総合的に論じたネット上の記事は多くないので話題のハードルを下げるとともに、もう一歩踏み込んでみようと思います。
カウルとは「バイクの車体の一部を覆う外装部品のこと。」です。
バイクには風防的な覆いがついているものがありますな。
これを「カウル付き。」といったりします。
昔は布の風防もありました。
それは「布垂れ風防。」とか言われていて、カウルとは呼ばないですな。
※ワタクシのはるか先輩の世代の話なのでよく知りませんが。
なので固定式の固形物が全面部についているバイクを「カウル付き。」と呼ぶようです。
カウルは主にABSなどの樹脂やFRP、カーボンなどの素材で作成されます。
■ABS樹脂
強度と耐久性、塗料の良さに優れるため仕上げが綺麗さな割に比較的安価で多くのバイクに採用されています。
現在の量産機のカウルは大抵これです。
■FRP(Fiber Reinforced Plastics)
ABS樹脂よりも強度が高く、作り方によっては軽量化が可能です。
※積層することで強度が変わるし重さも変わるので一概に高強度で軽量とは言えないのよ。
FRPの利点は、耐食性や耐候性に優れて長期間使用しても劣化しにくいと言われますが、
表面処理の質が悪いと雨天走行などで吸湿して伸び縮みするので塗装が割れたりします。
※ロータスヨーロッパのボディのFRPはすんごく質が悪いです。
■カーボン
最も強度と軽量性に優れた素材ですが、非常に高価です。
お金持ち仕様の高級車や本気のレーサーなどに採用されています。
これも表面処理が悪いと編み込み部が露出したりします。
※特に端部の処理ね。
カウルの素材にはいろいろあるということですが、
要するにバイクの全面についてて風よけ的な意味合いがある固形物であれば素材はなんでもいいっぽいです。
※昔のレーサーにはアルミ製のカウルもあった。
そのうち、転んでも割れなくて傷がつかない新しい素材ができるかもしれません。
※そういえばポリカーボネート製のカウルって聞かないよね。
こんな記事もあります▼
そうそう。
記事とは関係ないですがワタクシ事ですが20251023現在、絶賛インフルエンザを拗らせ中でして。
朦朧としながらブログ記事を書いているワタクシがいます。
よほど今週の記事追加は休もうかと思ったのですが、更新が遅いと 文句を言う 熱い声援のメッセージをたくさんいただきました。
なので、ものすごい無理して書いています。
インフルエンザ日記にでもしてやろうかと思ったのですが大人げないので、
熱い声援にお答えして 古い書きかけの記事を手直しして 公開することにします。
たまには温かい応援メッセージとかよこしやがれ。
もう一回言いますが
「今回はものすごい無理して書いています。」
そのつもりで噛みしめて読みやがれ。
※貴様ら無料で読んでるくせに図々しいぞ。 バイク女子のブログには優しいくせに。
ちなみに・・
カウル付きの反対はノンカウルです。
ノンカウルはそもそもカウルをつけない前提で作られたバイクのことです。
多くのカウルのないバイクはノンカウルというカテゴリです。
ノンカウルと良く混同されますが、ネイキッド呼ばれるカテゴリーもあります。
ネイキッドとはカウル付きバイクからカウルを取って軽量かつ安価にした車種です。
専用設計のフレームとかはありません。
※カウル付きとネイキッドでフレームの素材の違いはよくある。
ゆえに。
間違ってもZ2をネイキッドとか言ってはいけないのです。
そして。
Z1-Rのビキニカウルをユーザーが取り払ったものはネイキッドとは言いません。
メーカーが作ってないからです。
※Z1-Rのカウルレス仕様とか言いますな。
まあどうでもええ。
好きに言えばええ。
誰が言いだしたんだかわからんし、メディアも混同して使ってるし、たぶん誰も整理しないしまとめない。
※こういう記事を堂々と公開してるメディアは明らかに最近の資料しか見てないので信用なりません。
とはいえ。
メーカーも適当にネイキッドとか言ってたりするので売れりゃなんでもいいんでしょうな。
※でもバイク乗りと会話をしていて「この人、思慮が浅いな。」「特にポリシーはないんだろうな。」と思うのはこういう表現をしたときですな。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼
カウルの誕生と進化の歴史

それが公道用のバイクに搭載され始めたのは結構最近です。
少なくとも日本国内のバイクにカウルを搭載するのは「国の認可。」という規制との闘いだったのです。
意外にもカウルの歴史は古いのです。
1930年代にはすでにレース用のバイクには搭載されてた記録があります。
当初はライダーの風よけだったようで、空力とか関係なくほんわかしたか形のカウルがついていました。
※アルミを手でたたいて成型したモノだったようです。なので当時のカウルは銀色が多い。
その後、カウルが付いたほうが最高速が伸びるということに気が付き(笑)、空力を研究してそのノウハウがレースの世界に入ってきます。
空力の研究により、カウルが走行性能を向上させる要素として広がっていきます。
※アナログで行う風洞実験とか素敵。ワタクシはそういう研究する仕事に就きたかった。
最前線のレースの世界ではウイング的なものもつき始めましたが、
現在のフルカウルはどのメーカーも空力的に突き詰めた形状になっています。
そのため、
どのメーカー製でも同じような外観になりつつあります。
※一生懸命、他車との差を模索しているようですが素人目には色以外で判別できませんな。
こんな記事もあります▼
公道用のバイクで最初にカウルをつけたのはZ1-Rの時代と言われています。
※1978年ごろ。市販車最初の車種は何か?は諸説あるのだよ。
それから紆余曲折あっていろんな形状のカウルを持つバイクが出ては消えていきました。
現代は公道用でもカウルを装備したバイクは一般的になっています。
公道用バイクは競技するわけではないので、
それぞれのバイクの特性に合わせて各社が考えた最もいい形状のデザインとなっています。
カウルの形状がレーシングマシンに似てるほうが偉かったのは既に過去の話です。
※レプリカ一色だった時代はやっぱりおかしいのよ。
今のカウルはレーサーというスポーツバイクの究極系を頂点としてそれに近づけるより、
ライダーのライフスタイルに寄せてデザイン性が高いとか利便性が高いなど、いろんな方向に向かい始めた気がします。
むしろカウルの黎明期にあったようにデザインには多様性がありますな。
※公道にはレギュレーションがないので何でもありなのですよ。
こんな記事もあります▼
こんな記事もあります▼
ちなみに・・
現在のカウルはスタイリッシュで空力を考えたデザインになっていますが、昔のカウルは野暮ったいデザインが多いですな。
昔のカウルは野暮ったくてゴツくて重そうだけれどしっかり風防効果が有ったっぽいのです。
※初期のフルカウルとか野暮ったいけれど冷却風を邪魔しないとか結構考えられてて凄い。
下半身に風が当たらないように・・でもエンジンには走行風が当たるように・・みたいな工夫があったりします。
※これがかっこいいかどうかは別ですが。
昔のカウルが野暮ったい理由は、
と言った理由があったと思われます。
そのため、
当時のバイクメーカー各社が考えた最強のカウルとして、多種多様なデザインが存在したのです。
これらは次第に進化して、
といった時代のトレンドを反映していると言えますね。
※恰好良くないと売れないからね。
少なくとも、
空力を考えたスポーツバイクは物理の法則に従って100点のデザインがあるので、
どこのメーカーのカウルも似通った形になりつつありますな。
※メーカー名が入ってなきゃどこのメーカーかわかんないよ。
というわけで。
「見た目より、風防効果。」
「イメージ的に何となくレーサーっぽい。」
「レーサーそのもの。」
「スタイリッシュで効率を考慮。」
という感じにカウルのデザイントレンドは進化してきたと言えますね。
その一方で、
「カウルは風防性能よりもおしゃれアイテム。」
という空力とかどうでもいい流れはずっとあったっぽいですが。
昔のカフェレーサーにはいろんな形のカウルがついてるし、Z1-Rのビキニカウルは空力的にはアレだしね。
こんな記事もあります▼
カウルの何がいいんだろうね?

カウルの何がいいんだか具体的に説明できる人は多くないです。
風防効果ったってある程度の速度出さなきゃ意味ないですし。
まず、カウルには物理的なライダーへの風防効果があります。
カウルは物理的に風を遮断できるので高速走行時のライダーへの風圧を軽減することができます。
高速道路を延々と走る場合などはカウルがあると超楽です。
このような特性を突き詰めると、ライダーの前面を直接走行風からカバーできる大きくて立った形状のカウルになります。
このような形状のカウルを装備したツアラー系や最近のアドベンチャー系は上体を起こしたライディングポジションに合わせて設計されています。
※ ワタクシはは経験したことないけれど そういうカウルだと高速道路で雨に降られても濡れにくいそうな。
スーパースポーツやレーサーレプリカのような小さく低いカウルは高速道路では思い切り伏せねば効果はありません。
ずっと伏せたまま高速道路を走り続けるのは逆に疲れるのです。
カウルを装備すると走行性能的が向上します。
車体への空気抵抗や走行風の巻き込みを低減することができます。
バイクは複雑な形状なので走行中はいろんな方向から風(空気)が流れ込みます。
走行中にバイクにあたる空気を前から後ろに流すように整流することで走行時の安定性を増すことができます。
その結果として走行性能が向上するということです。
CB-Fインテグラとか初期の大型カウルは空気の整流より、ライダーへの風防性能を高めることを目的としたデザインですな。
今見るとゴツくてどうなのよ?って感じもしますが当時はカウルというだけで十分レーシーだったんでしょうねえ。
カウルがあるとハンドリングの向上も図れます。
ハンドル周りにメーターやライトなどの重量物をたくさんつけるとハンドリングが不安定になります。
いうなればママチャリのカゴに荷物を満載してる状態でコーナーに突っ込んでいくようなもので、
コーナーリング時のハンドルが不安定になります。
例として、
初期のビキニカウル装着車であるZ1-Rはビキニカウル周りにいろんなものを詰め込んだ結果、
ハンドリグ最悪マシンとして長らく不人気車でした。
当倶楽部のZ1-Rは 泣きながら そのネガな部分を打ち消すような改造を施しましたが、
試行錯誤を来る返した結果、峠を楽しく走れるレベルにするまで20年くらいかかりました。
※試行錯誤したので改造費はトータルすると100万円以上かかっています。
ハンドリングの悪さはライトやメーター、ウインカーやホーンをフレームマウントしたカウルにつけることで解決します。
ハンドル周りに何もつけないので重量によってハンドリングを邪魔されないため、自然なハンドリングにできます。
VFR400ZやCBR400FやFX400R、GSX400Xなどのライトが飛び出しているデザインはハンドリングの向上を狙ったものですよ。
※上記車種はカウルはありませんがカウルがない分、レイアウト的に非常にわかりやすいので例として挙げました。
どれもいまいち不人気なのは 格好悪いから 設計の意図が消費者に伝わらなかったためでしょうねえ。
こんな記事もあります▼
カウルがあるとデザイン的に視覚効果というかインパクトがあります。
カウルが設置されることで少ないバイクの塗装面が増えることでバイク自体のデザイン性が向上します。
この結果、バイク自体のイメージを変えることができます。
実際、フルカウルのレプリカとカウルを外したネイキッドでは全然印象が違いますね。
レプリカは塗装面が多くスポンサーカラーやメーカーカラーなどで比較的派手なカラーリングが多いですが、
ネイキッドはそれをやるとスポンサーロゴとかがちぐはぐになるのでシンプルなカラーリングが多い気がします。
カウルがあると追加装備を隠すことができる。
カウルがあるといろいろな装備を隠せるのです。
ハンドル周りにつけるとハンドリングの悪化とともにごちゃごちゃしそうなETCの配線とかUSB電源の配線とか。
古くは時計などもインナーカウルにつけたりしました。
※GSX750S3なんかはインナーカウルに小物入れがあったし。
いろいろ補器パーツの格納場所がないTZR250後方排気(3MA)なんかは冷却水のリザーバーなんかもここに格納してましたね。
3MAはピーキーで面白いバイクですがカウルがないと成立しないデザインのバイクだったのです。
ライバルのNSRはカウルレスにしてもそれなりに見れたのですが、
TZR候補排気はネイキッド状態にするとカウルで隠してた補器類が丸見えで格好悪いので人気がなかった、のではなかろうか。
※当時はコケてカウルがバキバキになるのでカウルレスに改造するまでが 様式美というか 割と普通だったのでした。
ちなみに・・
昔のスーパースポーツ系バイク(レプリカの初期の頃)のカウルは結構大きかったのです。
昔のレプリカほど、スクリーンが立った大きいカウルを装備しています。
というのは、
レーサーに似せたとはいえ、公道で使い勝手がいいものをメーカーが提供してたからです。
※初期のGSX-R1100なんてヘルメットがほぼぴったりはまる大きくて立ったスクリーンを装備してました。
ゆえに。
ライディングポジションも比較的ゆったりでツーリングにも使いやすかったのです。
※今思えばハンドルは低目でも、ステップは前目だったりとちぐはぐなポジションだけれど、当時はそれがレーシーだったのよ。
それが公道用のバイクでもレーシングマシンそのものの姿になっていく過程で次第にカウルは低くなっていったのです。
※ハンドルもレーサー並みに低いしね。
スーパースポーツやレーサーレプリカは性能的には素晴らしいかもしれないけれど、
あんまりとがりすぎて公道で使い勝手が悪いなら意味はないんですよねえ。
※そういうとがったバイクほど短期間で絶滅に瀕する傾向がありますな。
こんな記事もあります▼
カウルの種類とその特徴

サイドカウルやテールカウル、サイドスタンドカウルなどの話になると長くなるのでフロントカウルの話に限定します。
フルカウル
バイク全体を覆うように設計されたカウルです。
主にエンジンが隠れるものをフルカウルと呼ぶようです。
※GPZ900Rは戦略的にエンジンを見せるデザインだけど前面でアンダーカウルまで繋がってるのでフルカウルの一種と考えられます。
最近のレーサーやスーパースポーツと呼ばれる車種の多くはフルカウルを装備しています。
それは車体への空気抵抗を大幅に減らすことができるためです。
最高速やそこに至る速度、高速走行時の安定性に影響します。
※公道でもフルカウル車で高速道路を一定速度で走ると燃費もよくなるらしいね。
スポーツ性能を求めるほど、スクリーン部が低い傾向にあります。
伏せた状態でないとライダーへの風防効果は薄いです。
逆に大型のスクリーンや立ち気味のカウルの場合、
ライダーの全身を風圧から守るため、長距離移動の際に楽できます。
これはツアラー系とかアドベンチャー系に採用されてるカウル形式です。
スーパースポーツとツアラーの間に位置するバトルツアラー的なバイクもありますが、
どちらかと言えばスーパースポーツに近い低めのカウルが標準で、
自分でアフターパーツやメーカーオプションの立ったスクリーンに変更するみたいなのが多いです。
なので、
デカくてハイパワーなツアラー的なカテゴリーのバイクの設計思想はスポーツバイクに近いと思われます。
フルカウルの副産物として、
フルカウルのバイクは真冬に走るとエンジンからの熱がカウルにこもるので比較的暖かいです
それとフルカウルのバイクはステッカーを張る場所に困らない(笑)
ハーフカウル
ハーフカウルは主にエンジンから上のハンドル周りを覆うように設計されたカウルです。
ハーフカウルはフルカウルのようにフレームマウントされるのが一般的です。
※AR125Sみたいなハーフカウルっぽいハンドルマウントのビキニカウルもある。
エンジンは見えてるけどライトなどの補器はカウルに付いてるのが普通です。
※過渡期にはメーターなどがハンドルマウントされてるハーフカウル車もあるけど。
当たり前ですがハーフカウルはフルカウルに比べて熱がこもりにくいですが空気の整流効果もそれなりです。
※何せ下半分はノンカウルと同じですし。
放熱を大気に頼る空冷バイクに大きなカウルをつける場合、ハーフカウルになりがちです。
※例外としてCB1100Rや油冷のGSX-Rがあるけれど両方とも渋滞には弱いです。
以前は、フルカウルのバイクのセンターカウルやアンダーカウルを外した状態もハーフカウルと言っていました。
※ワタクシが乗ってた初期のGSX-R1100のカウルはアッパーカウルとセンターカウル、アンダーカウルで構成されてるので季節ごとにカウルのつけ外しをしてました。
また、
カウル自体がタンクからつながるデザインと割り切った設計の車種もありました。
これらは小ぶりなカウルがついていますが、風防効果はそれなりです。
FZ250フェーザーとかVT250FG、FHなんかはハーフカウルのカテゴリーでいいかと。
※フェーザーはアンダーカウルをつけたバリエーションの 今となっては超レアな フルカウルもあるけれど、逆に不自然。
ハーフカウルはメリットもデメリットもフルカウル以下と言えますな。
※要するにいいとこどりというか中途半端というか。
ただし。
街乗りレベルではハーフカウルで十分です。
バイクの性格上、ハーフカウルのバイクはアップハンドル仕様のバイクも多いです。
公道では低いハンドルより絶対に使い勝手がいいです。
下半身に風が当たるとか当たらないとか一般公道を走る以上、誤差の範囲です。
ハーフカウルでも追加装備の配線とか十分隠せますし。
※当倶楽部のVT250FHは小ぶりなハーフカウルですがUSB電源とか電圧計とか温度計とかハザードシステムなどをスッキリ収めています。
フルカウルのコストと実用性、効果が高速走行に限定されることを考えればフルカウルは趣味性の高い贅沢品ですよ。
※もちろんデザイン的にフルカウルが好き!というならそれも結構だと思いますが。
こんな記事もあります▼
ビキニカウル
ビキニカウルはヘッドライト回りを覆うように設計されたカウルです。
一般公道用のカウルはコレから始まりました。
最初のビキニカウルは新しさと物珍しさとレーサーっぽさでウケたようです。
カフェレーサーにもこぞって搭載されてたようですし。
※ スポーツバイクとして致命的なハンドリングの悪化をどうにもできなかったので あっという間にハーフカウルに駆逐されましたが。
カウル黎明期のビキニカウルは個性的なデザインが多いです。
ワタクシはビキニカウルのRZ250Rとか本当に好き。
Z1-Rに乗ってるし、昔はAR50Sにも乗ってたしビキニカウル乗りになる運命だったと思っています。
※たとえハンドリングが悪くて乗りづらかったとしても、誰も乗れないマシンに乗ってる♪という優越感すらある♪
それに。
個性的なカウルという時点で他人との差別化ができてすばらしい♪
※たとえ人にダサいと言われようが構いやしないのです。
良くビキニカウルの風防効果はどうなの?と言われますが 当たり前ですが 大きさによります。
※どうやってもあなたの身体より小さいビキニカウルに風防効果を期待するほうがおかしいのよ。
風防効果よりもカッコいい外観を演出することの効果が高いのですよ。
好き嫌いは分かれますがビキニカウルを装着するだけでノンカウルとは違ったイメージになります。
それに。
ビキニカウルは小さいとはいえ、追加補器類を隠すには十分なスペースがあります。
当倶楽部のZ1-RにはシガーソケットやUSB電源のほか、ドラレコのモニターすらついています。
※ハンドリングの追及はどうした?って感じですがそろそろ楽したいのよ、ワタクシも。
ビキニカウルは安くて取り付けが割と簡単なので、カスタムパーツとして人気があります。
適当につけちゃうと走行時に落ちたりして危ないのできちんとつけましょう。
※汎用性を高めるために適当な固定方法の安価な後付けビキニカウルが大量に出回っています。
Bandit400Vを新車で買ったY君は勇んでビキニカウルを追加装着したのですが、
後期型で純正のロケットカウルやビキニカウル付きが出ちゃって可哀そうでした。
※大丈夫、初期型の400Vのほうがシュッとしててかっこいいって(笑)
こんな記事もあります▼
ライトバイザー
ライトバイザーはヘッドライトの上に取り付けるスクリーンです。
※カウルに含まれるかどうか微妙な線ですが。
VT250FC(初期型)やVF400F、MVX250Fなどはビキニカウル的なものを「ライトバイザー。」と言い張って国の認可を取ったのは有名な話ですな。
※この頃のHONDAは世界一のバイクメーカーだけに挑発的なチャレンジをよくやってて面白いよね。
ライトバイザーはビキニカウル以上に取り付けが簡単で安めなので改造パーツとして人気がありますな。
特に古臭いデザインのバイクには絶妙に似合うのでよくつけられています。
ただし。
風防効果は大きさなりです。
配線などはほぼ隠せません。
なので。
「見た目重視のカスタム。」というレベルを出ません。
でもそれでいいんですよ。
自分がかっこいいと思えば。
爆音立てて人様に迷惑かけてるわけではないし、法的に問題なければ自己満足でいいのです♪
※そういえばGSX1100S刀についてるやつもライトバイザーの一種と思われます。正式にはスクリーンとか言うんだっけ?
ちなみに・・
カウル付きでないとバイクじゃないみたいな時代がありました。
当時は初心者や女子など猫も杓子も流行に乗っかってカウル付きバイクに乗ってたわけですが実はカウルにはデメリットも多いのです。
などなど。
そんなわけで。
カウルのないバイクのほうが好きだという人は結構多いです。
昔も居ましたが時代的にそういう人は明らかなマイノリティでした。
今でいうと、
「生き物みたいな造形や異形のライトを装備した最近のバイクが嫌い。」
みたいなもんです。
いつの時代もマイノリティは存在するのです。
それでも。
万人受けしようがしまいが、カウルは法的に認可されています。
その範疇なら乗り手が好きなバイクを選んで乗ればいいのです。
いちいちネットで検索して人の評価を見てる場合じゃないのです。
誰でも乗れる人気車と一緒に格好つけて写真撮るよりも、
維持が難しいけど自分の感性に合う不人気車にまたがってダブルピースしてる破壊力のある写真のほうがワタクシは好きです。
なんでも人の評価を気にしすぎると人生面白くないのです。
まとめ

バイクを買うときはそれを踏まえたうえで選んでいるんだろうと思います。
カウルがあろうがなかろうが、最終的には自分の価値観で好き嫌いでいいと思うのです。
カウルは種類にかかわらず、大きいカウルほど高速走行時にライダーへの風圧を軽減します。
※そりゃそうだ。
走行風は常にライダーの体温を奪い続けるのです。
そのため、バイク乗りは風圧によって疲れるのですよ。
長距離を高速で移動する際はその影響が顕著になります。
カウルによって持続する風圧を軽減すると楽ちんだし快適なのです。
これがライダーの集中力を維持してくれればいいのですがあんまり楽だと眠くなったりします。
これもデメリットかもしれませんな。
※ワタクシはツーリング途中で眠くなったら休憩して寝ちゃう派です。若いころは田舎のバス停のベンチとかで寝てました♪
カウルは種類にかかわらず、大きいカウルほど高速走行時に車体への空気抵抗を軽減します。
空気抵抗が少ないほど、高速走行時の加速性能や最高速度が向上しますし、
空気抵抗が少ないほど、車体の安定性や燃費向上に効果があります。
※ただし、横の面積が大きいカウルだと横からの風にも弱いのよ。トラック抜いた後とかトンネル出た直後とかさ。
ただし。
「空気の抵抗については高速走行しないとカウルの恩恵はほとんどない。」
と言えます。
※逆に言えば一般道で法定速度で巡行するならカウルがあろうがなかろうがあんまり関係ないのです。
メリットとして大きいのは、
フレームマウントのカウルの場合、カウルの内側にいろんなものを取り付けられます。
メーターやライト、ウインカーやホーンなどがそれです。
ハンドリングの改善に超効果が有ります。
初期のXLR250bajaの出目金ライトはハンドルマウントでしたが、XR250Bajaになってフレームマウントになったのはそういうことなのです。
※Bajaはカウル付きではありませんが例としてわかりやすかったので。
それにカウルの内側に配線を隠せたりします。
これはビキニカウル程度の大きさでもできるし、非常に効果が高いです。
とにかく追加装備の配線プラプラしてるバイクはダサいのですよ。
※聞いてるか?シートとタンクの隙間から配線だしたまんまツーリングしてるCちゃんよ。高価なKTMのツアラーが泣いてるぞ。
カウルが一般道の普段使いでありがたいのは、
カウルが空気の層を作るため、エンジンの熱が逃げにくくライダーが温かいことです。
冬はこれでいいのですが、真夏は地獄になります。
※ストーブ抱えて走ってるみたいなもんです。しかも長袖長ズボン+ヘルメットです。
もちろん、
フルカウルは本当にあったかいですが、ビキニカウルにはその恩恵はほぼありません。
明かなデメリットとしては、
と言ったところです。
このようにカウルにはメリットもデメリットも数多いのです。
それでも。
カウルにはいろんな種類がありますが好きなのに乗ればいいのです。
デメリットとして書いた項目でも好みの範疇ですので気にしなくてよろしい。
※そういうデメリットをむしろ好む変態しかバイクに乗らない、というのも正論ですし。
人様に迷惑が掛からない範囲なら何でも好きにやればいいのです。
それくらいの制約があったほうがむしろ自由なんですよ。
なんでもOKで個人の好きなように自由にやってもいい!というのはただの混沌ですので、法治国家には向かないのです。
とにかく。
カウルは公道を走る分には別にあっても無くてもいいのです。
というわけで、とにかく贅沢な装備だということです。
ちなみに・・
カウルはバイクの大きな面積を覆う樹脂ですよ。
バイクは転倒するのが宿命です。
そんなの割れたり削れたりしないわけないじゃないですか。
カウルは大小に関わらず、転倒するとほぼ確実にダメージを受けるのです。
そうなったときに、
カウルを交換したり修理したりするとすんごく高いのです。
昔はフロントカウルで原付スクーターが買えると言われていましたが本当です。
※「こち亀。」でもRG-γのカウルでジェンマが買える、みたいなネタがあったくらいだし。
カウル自体を修理するにしても莫大な修理費用になりやすいです。
※なのでメーカーに在庫があれば交換が手っ取り早いしむしろ安くつくことが多いです。
そもそも樹脂やFRP、カーボン製のカウルは修理が難しく、
普通のバイクショップで修理を引き受けてくれるところは少ないハズです。
そして。
カウルは車種ごとに専用パーツが多いです。
同じ車種でも年式によって微妙に形状やカラーが異なったりします。
当然、古くなればなるほど純正部品は欠品になり入手が困難になります。
カウルはタンクやメーターなどと同じように目につくパーツなのでメーカー欠品になりやすい。
まともな状態の中古パーツがあるとは思わないほうがいいです。
※人気車種のカウルは中古市場で宝石のような値段で取引されてたりします。当然、状態がいいほど高いです。
カウル付きバイクの場合、売る時も買うときもカウルの傷がポイントになります。
売る時に大きな傷があるとめちゃめちゃ買い叩かれます。
さらに。
こけた時のダメージはカウル以外にもスクリーンやウインカー、ライトやメーター、カウルステーなどにも及ぶ場合もあります。
細かいパーツまで新品でそろえるとなるとパーツ代がかさみ、修理代は余裕で中古バイクが買える値段になることもあります。
修理代が高すぎてドン引きし、バイクから気持ちが遠ざかって修理せずに放置、という話も良く効く話です。
大借金してカウル一式を直したとしても、またすぐコケたりしますしねえ(笑)
※そういうもんです。
昔の小僧どもはカウルをガムテープで固定して乗ってたりしたもんですが、大人でこれやるとものすごく貧乏くさいです。
※ああいうのは小僧がやるからかわいいんですよ。
当然デカいカウルのほうが修理代も高い傾向にあります。
フルカウルなんてフルセットで買ったらもう大変な出費ですよ。
カウル付きのバイクに乗るということは、そういう覚悟が必要ってことです。
なので。
少なくともバイクに慣れるまではノンカウルのバイクがいいんじゃなかろうか。
出来ればコケてもダメージが少ないオフ車とかが安くてよろしい。
と、思うのだけれど、バイクなんて趣味趣向の世界ですので一番いいと思うものに乗ったらいいのです。
たとえ、維持費が高くつくとしても、です。
最近、なんでもコスパとか言ってるけれど、
「コスパがいいというのは値段にわりにはいい感じ。」
の域を出ないので自分の欲求を完全に満たしてないのに我慢して言ってることが多いように見えるんですが。
結局、ワタクシはいろんな経験をした結果、
「買う理由が値段なら買わない。買わない理由が値段なら買う。」
といった選択をしたほうが最終的に後悔が少ないという結論に達しております。
※結局それがコストに見合う満足なわけで、コスパもいいってことになるのだね。