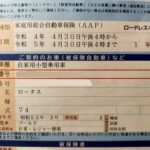タンクにガソリンはあるのにセルは回るのにプラグに火花が飛んでるのに初爆がない。
もしかすると負圧式ガソリンコックではないですか?
こういう場合、エンジン始動にはコツがあるのですよ。
当記事の目次
「負圧式ガソリンコック。」とはなんだ?

「負圧式ガソリンコック。」にすると使い勝手が上がるのです。
数値的な性能アップではありませんがこれも性能ですよ。
かつてバイクのキャブには、
ガソリンはガソリンタンクから重力で自然落下して、
単純なガソリンコックを経てキャブに供給されていました。
何せ構造が単純なので古いバイクはこのタイプが多いです。
※Z1系とかRZとかね。
ガソリンコックをONにするとガソリンが流れるタイプはこのタイプです。
もちろんガソリンコックをOFFにしないでホースを外すとガソリンが駄々洩れします。
これを
「自然落下式コック。」
とでも言いましょうか。
キャブ内部の「フロートバルブ。」という小さな部品が、
重力でキャブ内に入ってくるガソリンの流量を制御しています。
このため、
この小さなパーツがダメになるとキャブからガソリンが溢れ(オーバーフロー)まくります。
※この手のバイクは1日単位でエンジンを止めるときはガソリンコックをOFFにするのがセオリーですよ。
こんな記事もあります▼
「自然落下式コック。」ではガソリンコックのモードをON-RES-OFFにセレクトができます。
となっています。
こんな記事もあります▼
80年代中盤。
「負圧式ガソリンコック。」が登場します。
※それ以前からあったのかもしれませんがワタクシは知りません。
このタイプはガソリンコックがONのまま、ホースを外してもガソリンが垂れません。
エンジンのシリンダー内のピストンが上下する際の負圧を利用して、
ガソリンコックの弁を開け閉めしてキャブにガソリンを供給します。
※エンジンから生えたホースがガソリンコックにつながってるのが「負圧式ガソリンコック。」です。
具体的には、
エンジンのシリンダーからホースが伸びていて、ガソリンコックにつながっています。
このホース内の負圧が高まるとガソリンコック内のゴムの弁を吸い寄せるように開きます。
その隙間をガソリンが流れるのですな。
逆に言えば、
「負圧式コック。」はONでも負圧がかからないと弁が常に閉まっているため、
ガソリンホースを外してもガソリンが流れないのです。
とまあ、結構凝った仕組みなのですよ。
利点はイチイチ駐車する際にガソリンコックをオフにしなくてもいいということです。
なにせ、
エンジンが動いてない時にがガソリンが流れないのでライダーはガソリンコックの閉め忘れがないのです。
運用時の面倒くささがないのですな。
負圧式コックではガソリンコックのモードをON-RES-PRIにセレクトができます。
となっています。
こんなに大事なことなのに意外とこれをわかってないバイク乗りが多い。
※もはやキャブ車なんてないので知らなくてもいいのかもしれませんが。
こんな記事もあります▼
ちなみに・・
言っておきますが、
「負圧式キャブと負圧式ガソリンコックは全然違う。」
ので要注意です。
なんとなく似ていますが完全に関係ない別物です。
キャブについては語ると長くなるのでココでは詳細は書きませんが、
負圧キャブというのは、
という流れです。
※用語とかわかんなければググれ。そのうち記事でまとめる・・けど文章で書くの面倒くさい。
要するにシリンダーの負圧でピストンバルブの開度を決める方式です。
なので。
アクセルワイヤでダイレクトにスライドバルブを開く強制開閉キャブより、ダイレクト感が薄いと言われます。
でも負圧式キャブは結構昔からあって、HONDAのS800にも採用されてたりします。
※古い英国車のSUキャブは代表的な負圧式キャブですし。
というわけで。
負圧式キャブは負圧式ガソリンコックとは関係ないのですよ。
こんな記事もあります▼
「負圧式ガソリンコック。」搭載のバイクがエンジンがかからない理屈

これは機構的な宿命です。
ガソリンは時間とともに気化して減ります。
※ガソリンは変質してしまうとかなり厄介ですので気化で無くなったほうがマシですが。
当然、放置期間が長いほどガソリンは気化が進みます。
キャブ内のガソリンが気化するとエンジン始動のために必要な油面が保てなくなります。
コレが負圧式コック車のエンジンがかかりづらい原因です。
1週間ほど放置したキャブ内の油面は確実に下がっています。
※夏は特に気化が速いです。
こうなるとキャブ内の油面を上げなければエンジンに混合気が回りません。
当然エンジンはかかりませんね。
とにかく。
エンジンがかかるほどガソリンがキャブ内にないので、
チョークを引こうが押し掛けしようがエンジンはかからないのです。
※ガソリンタンクにガソリンが入っていてもキャブの内部ではガス欠状態ということです。
大抵の人はこうなると「エンジンがかからない。」という判定をします。
こういう場合でも基本的にセルモーターは連続で5秒程度までしか回さないほうがいいですよ。
※バイクで一番電力を食うのはセルモーターです。連続使用を考慮されてないのですごい熱を持ったりします。
ちなみに・・
「負圧式ガソリンコック。」は何がいいのか?
ひとえに。
「エンジンのシリンダーが動かない限り、キャブへのガソリン供給が絶たれる。」
です。
「自然落下式コック。」はセレクタをONやRESにしてると、
ガソリンタンク内のガソリンがONやRESによる物理的な限界まで、
キャブにガソリンを投入し続けます。
キャブ内で揮発したガソリンの不足分が常に供給されるということです。

Z1-Rのガソリンコック。
もちろん自然落下式の純正品です。
※Z1-RはZ1系では珍しくキャブにつながるガソリンラインは1本です。
実はこれが放置車両のキャブを詰まらせる最も大きな原因です。
※放置車両のレストアで最も苦労するのはココ、と言っても過言ではないのですよ。
というのも。
キャブ内部でガソリンが気化して減って変質してを繰り返すと、
変質した粘度の高いガソリンでキャブの導通路が埋まっていくのです。
とんでもない異臭がします。
こうなるとどうやってもキャブ本来の本調子を取り戻すのは難しいです。
経験上、こうなったキャブが完全に本調子に戻ったのを見たことはありません。
※キースターのキャブリペアキットでもキャブボディの細かい穴に詰まった変質ガソリンには対処できませんしねえ。
キャブレーターをいい状態にキープするコツは、
鮮度の高いガソリンを流し続けることですよ。
古いバイクを長い間大事にしてるオーナーはこういう所に非常に気を使っています。
以前から大容量タンクで燃費が良く、給油回数が少ないことを誇るバイクがありますが、
ガソリンの変質を考えたらタンク容量は少なめで常に鮮度の高いガソリンを入れてるほうがキャブにとってはいいのです。
※もちろん「自然落下式コック。」のバイクの場合、長時間エンジンをかけない場合はOFFにすべきですよ。

Z750D1のガソリンコック。
当倶楽部のZ750D1のガソリンコックは純正ではありません。
純正は次第に動きが渋くなってセレクタを動かしずらいし、下手すりゃ折れる。
最近のバイクはキャブではなくインジェクション方式です。
燃料ポンプでインジャクターにガソリンを圧送しているので、
どういう扱いがベストかは知りません。
でも確実いえることは、ガソリンは気化するし変質するのです。
電子制御の燃料系でガソリンが腐った場合、どうなるのかね?
※とんでもない修理代を請求されそうですな。
こんな記事もあります▼
「負圧式ガソリンコック。」搭載のバイクのエンジンをかけるコツ

そのため、エンジンがかかる程度にキャブ内部のガソリンの油面を上げるためにはガソリンをキャブに流さなければなりません。
キャブはかなりデリケートなセッティングの下で稼働しているので、
油面が下がってるとシリンダーからの負圧でガソリンを霧化できません。
※キャブの内部でガス欠と同じ状態になっているからです。
当然エンジンはかかりません。
油面が下がってるキャブのバイクに対して、
エンジンはかかることはないのです。
これを踏まえて。
「負圧式ガソリンコック。」搭載のバイクで、
タンクにガソリンが入っていてセルが勢い良く回るにもかかわらず、エンジンがかからない場合、
まずは落ち着くことです。
※人生と同じで焦るとろくなことがありません。
ガソリンコックのセレクタをPRIにしてしばらく待ちましょう。
その間にキャブにはガソリンが供給され、10秒もあればキャブ内の油面が上がるはずです。
油面が上がったころ合いを見計らって、
コックをON(もしくはRES)にしてセルを回せばいいだけです。
そういう設計なんですよ、負圧式のガソリンコックというやつは。
なのに。
実際は、
エンジンがかからなくてもセルを回し続けて何とか起動してる人がほとんどではないでしょうか?
※素人め。
これは、
という流れを無意識にやってるからです。
これでも悪いわけではないのですが、
下手すりゃセルの回しすぎでバッテリー上がります。
※セルモーターが動くときの負荷ってかなりデカいのです。
とはいえ。
「負圧式ガソリンコック。」の仕組みを知らなきゃそれしかやりようがないわな。
バイク乗りには知識が必要なんですよ。
キャブ仕様のバイクというのは、
「乗り手にそれなりのポテンシャルを求める。」
乗り物なのです♪
キャブレーター車のオーナーは自然にできてることを誇りに思いましょう。
一方、
「自然落下式コック。」
ではONにしたと途端キャブにガソリンが流れ込むので、
キャブの油面はシリンダーからの負荷とは無関係に油面が上がります。
※全然関係ないですが「太陽の牙ダグラム。」の黒幕というか悪役の名はラコックですな。
そういう意味では原理が単純なだけにわかりやすく、楽なコックと言えます。

セロー225SWのガソリンコック。
凝った作りのガソリンコックが時代を感じさせますな。
自然落下式なくせにエンジンの始動性はよくないのはたぶんキャブのせいです。
※環境性能対策でマイナーチェンジのたびにキャブは変更されてるのだ。
ただし。
前述した通り、長期間放置する場合、
ガソリンコックをOFFにしないとキャブ内のガソリンが変質し続けて再起不能になるリスクがあります。
※1週間程度でもガソリンは変質しますよ。大気中に2週間放置したガソリンを使うと本来の性能が出ない、なんてレース関係者もいます。
ちゃんと設計に基づいた要領を守った使用をすればいいだけのことですが、
ちゃんとできてる人は意外と多くないです。
※キャブ車全盛の時代でも知ってる人はほとんどいなかったし。
こんな記事もあります▼
ちなみに・・
今までほぼ廃車レベルの放置車両を何台も路上復帰させてきたワタクシです。
そのほとんどは「自然落下式コック。」だったのでキャブの中身はぐちゃぐちゃになっていました。
どんなに洗浄してもキャブの本調子が出ず、キャブ自体を丸ごと交換して対処してきました。
※取り替えたキャブは予備の部品取りとして保管してあります。
が。
今はキャブレーターの時代ではないのです。
メーカー純正の新品キャブレーターは欠品になって久しいです。
中古でもまともなキャブが入手できるわけもない。
※断言しますがヤフオクなどに出てる中古のキャブは9割がまともに動きませんよ。かなり割の悪いギャンブルです。
が。
「負圧式ガソリンコック。」搭載のV250FHのレストア時に分解したキャブはかなりきれいだったのです。
ガソリンタンク内のガソリンは超変質してたし、タンクは錆び錆でしたが。
これは放置期間中ずっとガソリンの供給が絶たれていたからですね。
キャブを軽く清掃したらちゃんと動きました。
つてを頼ってVT250FH用の新品キャブ(デッドストック品)を入手しましたがもったいなかったかな。
※予備のキャブは貴重なので完全な無駄ではないにせよ。
このように。
「負圧式ガソリンコック。」って結構すごいことなのですよ。
ワタクシ的には バイクは放置されがちな乗り物なので かなりの発明だと思っています。
ま、知らなきゃありがたみはわからないんでしょうけれども。
こんな記事もあります▼
もっと乗れよって話です

でも「負圧式ガソリンコック。」でもエンジンがかかりやすい個体もあります。
その多くはオーナーが頻繁にエンジンをかけている場合がほとんどです。
バイクのエンジンがかかない場合、セルボタンを押しまくって何とか始動している人が多いです。
ツーリングクラブでの月一回の恒例ツーリングの朝にエンジンがかからない、なんてパターンは数知れず。
※昔からそういう人はいましたが。
そりゃたまにしか乗らないんだからそういうこともあろうて。
ガソリンが気化して減る前に乗ってやれば再始動が楽なんですがね。
そういう特性を知らずに、自分のバイクはエンジンがかかりずらい、と思い込んでる人もいますな。
※でも宿泊ツーリングで翌日もバイクに乗る時は始動性がいい、という経験はあるはずですよ。
たとえオフシーズンでもバイクのエンジンは週一程度でかけたほうがいいんですよ。
前述した通り、鮮度の高いガソリンをキャブに回して油面を確保してやるために、です。

Z1-R。結構圧巻ですぜ、雪の壁
寒くてもできるだけエンジンをかけてやりたいのだ。
出来れば数キロでも乗ってあげるとキャブもバッテリーも長持ちします。
とはいえ、長野の冬にバイクに乗るのは自殺行為でもあるのでお勧めはしません。
でもエンジンをかけるくらいならできるでしょう。
当倶楽部では真冬でも2週間に一度程度、イチイチバッテリーを積み直してエンジンを始動することにしています。
※夏は2週に一度、草刈りをしています。その頻度で草を刈らないと野生の王国になってしまうのですよ。
ちなみに・・
負圧の話が出たのでついでに。
車のブレーキには倍力装置的な機能「ブレーキサーボ。」があります。
これにより、軽い操作でそれなりの速度で走るくそ重い車を片足のペダル操作で簡単に減速できるのです。
※ブレーキサーボがない車は力いっぱいブレーキペダルを踏まないと止まりません♪
このブレーキサーボを稼働させるにもシリンダーの負圧を利用しています。
※今の車は知らないけどちょっと前まではこの方式が主流。
なので。
どこかふんわりしたブレーキタッチだったりしたものです。
ワタクシが3代目プリウスを借りた時に感じたかっちりしたブレーキタッチによる違和感は、
電気的なアシストをする倍力装置によるものでした。
※ハイブリッド車は常にエンジンが動いてるわけではないので電気的なアシストとしたようですな。
これからの車はかっちりタッチのスイッチ的なブレーキになるんでしょうねえ。
ブレーキには前輪に荷重を集中させたり、軽く引きずったまま走るみたいなテクニックもあるのですがね。
※今後はこの手のテクニックは誰にでもできる電子制御になるんですかね?
「ブレーキはスイッチじゃねえぞ(笑)」
というヤジや笑いのネタは将来なくなるんでしょうねえ。
※ワタクシ的にはこの話だけで1本記事かけますがマニアックすぎるので遠慮しておきましょう。
まとめ

扱いにはコツがありますが慣れればどうということはありません。
これを当然の様に使いこなすのがキャブ車乗りですよ。
既に市販されているバイクのほとんどに搭載される気化器はインジェクションになりました。
90年代終盤くらいまではキャブレーター搭載車がメインだったのですよ。
※一部例外はありますが。
少し前から流行っている けど、もう終わりっぽい 旧車には大抵キャブレーターがついています。
時代の流れ的にしょうがないとはいえ、現実的にはまだまだキャブ車は実在しています。
※キャブ搭載の車はほぼ絶滅しましたがね。
2週間ほど放置してエンジンがかかりずらい場合でも
知識があれば慌てずに対処できるし、
無駄にセルモーターを回してバッテリーに負荷をかけることも、
無駄にキックして体力を消耗することも、
ないハズなんですよ。
久しぶりにバイクに乗ろうとしたらバイクのエンジンがかからない!
こういう場合はキレたり凹んだりせずに落ち着いて理屈を考えて対処すればいいのです。
・・まさか自分のキャブレーター式のバイクのガソリンコックが、
「負圧式ガソリンコック。」か「自然落下式コック。」か知らないなんてことはなかろうな?
※ガソリンコックのセレクタにPRIがあれば負圧式だと思ってよろしい。
こんな記事もあります▼
ちなみに・・
当倶楽部に所属するバイクで「負圧式ガソリンコック。」搭載車は唯一VT250FHだけです。
そういう意味では1986年式だけど最新鋭(笑)
※DT200WRやKDX125SRは年式は新しいけれど、負圧が少ない2stなので自然落下式ガソリンコック搭載です。
最新鋭のはずのVT250FHですが、
2週間程度エンジン掛けないとエンジンの始動が明確に悪くなるのです。
外気温とかチョークとか関係なく、始動しようとしても完全に初爆がない状態なのです。
もちろん、セルを数秒単位で何度か回せば始動しますよ。
この方法でもいいのですが、バッテリー自体が小さいのであんまり負荷をかけたくないのですよ。
※遠征先でセルが回らなくなって焦ったことがあるので。
そして。
いったん始動した後は全く問題なくあっさりエンジンが始動します。
これはどういうことなのか?
いろいろ考えた結果、
「そういや負圧式ガソリンコック搭載だったな。」
ということに気が付きました。
で。
わざと2週間ほど放置してガソリンコックをいったんPRIにして10秒待ってからセルを回すと、
あっさりエンジンが始動するのですよ♪
これは当記事で書いたように、
ことにより、
ということですな。
なんでも理屈があるのですねえ。
ガソリンの流れは見えないけれど、そういう理屈で動いてるんですねえ♪

VT250FH。
当倶楽部に来た時はほぼ廃車だったにもかかわらず、よく復活したよなぁ。
今では当倶楽部一番のツーリングマシンとなっています。
すんごく古いバイクには、
「ティクラー。」
というキャブ内にガソリンを満たすためのポンプがあったりしますしねえ。
※W1とかそうだったと記憶しています。

DT200WR。
世間的にはエンジンがかかりにくいと言われているDT200WRですが、当倶楽部の個体は全くそんなことはありません。
キックアームが短いのでエンジン始動にはコツは必要ですがね。
※日頃のメンテのたまものだと思っております♪
そうそう。
こういう「エンジン始動の儀式。」というのは旧車にはつきものです。
車でもキャブ車の場合、
車種毎の知らなきゃエンジン掛けられない車も多く存在します。
※とはいえ、個体毎にまた違うのが生き物っぽくて個性的なのが旧車です♪
というのが当倶楽部のロータスヨーロッパにおけるエンジン始動の儀式です。
※各工程の加減はワタクシにしかわからないので、天然の盗難防止装置と言ってもよい。
慣れてくるといつの間にかこのような手順が普通になってきますが、
一般人には何をやってるのか不思議に見えるようですな。
やっぱり、古い車やバイクは乗り手を選ぶのです♪
ハードルはそれなりに高いけれど、その分満足度というかオーナーであることを実感できますね。
旧車オーナーたるもの、エンジンがかかりづらいくらいででイチイチ慌てたり腹を立てててはいけないのです。
それが出来なければ旧車なんて無理なんですよ。