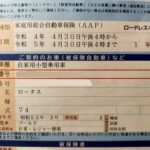70年代の旧車はそんなに複雑な電装のシステムを積んでいるわけではありません。
半導体とかセンサーとかまるでありません。
基本はスイッチ入れたら電球が光ったり、モーターが回ったりするだけ。
素人にもわかりやすいです。
配線図とか単純なので「バイクみてえ」と思っちゃったりします。
※miniERAターボの電装がひどかったので何があっても動じないワタクシは育ったなぁ、と感慨もひとしおです。
このようなニッチすぎる記事がワタクシは大好きだ♪
当記事の目次
ロータスヨーロッパの電装・スイッチについて
とにかく全般的に安っぽいです。
もうね、秋葉原ラジオ会館で買ってきたのか?っていうくらいです。
いや、ラジオ会館に失礼だ、という安っぽさです。
ほぼすべてがギボシで接続なのでわかりやすいです。
※いかんせん安っぽすぎます。
せめてカプラーとかコネクタとか使ってよ・・と思う箇所もあります。
外車はコネクタが死んで断線する
というのもよく聞くのでこれはこれでよかったのかな?と思ったりします。
※おかげで中学生程度の電気配線読めれば対応可能なのもうれしいです。
ロータスヨーロッパの純正のヒューズボックスは右側席の左足部分の内装内側に埋まっています。
とにかく狭いので配線のやり直しとか面倒なことこの上ないです。
っていうか、
ほんとにここでいいのか?
という位置です。
4系統しかないヒューズ
イギリスは何か?
ヒューズは4本までとかいう法律でもあったのか?
この少ないヒューズを各配線で使いまわしてるもんだから電気の流れを追うのが逆に面倒くさいです。
ちなみに・・
ヒューズボックスのヒューズが4系統しかないのは旧miniも同じです。
こちらは長い歴史の間にかなり無理やり電装を追加、ラインヒューズを増設してきた歴史があります。
メインヒューズボックスの4系統以外にもラインヒューズがあります。
※マジで余計わかりづらい。後付感が半端ないです。
しかも!
このラインヒューズのホルダの精度がひどくて接触不良を起こします。
英国車のヒューズは全部見直した方がいいですよ。
ロータスヨーロッパに追加した電装について
ワタクシの場合、純正ヒューズボックスは廃止しています。
新たに汎用ヒューズボックス8系統×2で作り変えました。
※純正ではパワーウィンドウにヒューズ入ってないぜ♪

ココしかつけるところがなかったけど、これ付けるのもアクロバティックな動きを要したのだった。
とにかく乗車スペースには設置できる場所がありません。
トランクに移設することも考えましたが、純正然としてた方がスマートかと思いまして。
センターコンソールの灰皿の裏側、ヒーターの配管の隙間にスペースを確保して取り付けました。
※グローブボックスを切り欠いて作ろうかと思ったけど度胸がありませんでした。
これで、ファンの増設や、グローブボックスの明り取り照明などに対応させています。
※メンテナス性は最悪なのでそのうち作り変えようかと思います。

ETCについても無理やり右ハンドルの運転席の奥に設置しました。
まじめにつけるところがないので散々悩みました。
※ヒーターコアにベルクロのベースをつけて載せた感じ(配線がもう酷いことになってるんですよ、この辺)です。
また、
シートヒーター&クーラーを増設するのにシガーソケットがほしかったので増設しました。
これもとにかく位置決めが面倒でした、。
一箇所は、前のオーナーが灰皿横に無理やり穴をあけて作ってくれたいたのでこれをそのまま使っています。
もう一箇所はサイドブレーキステッキ周りに無理やり固定しました
※ほかに設置できる場所がない
ちなみに・・
最近は何でもかんでもUSBで充電、電源供給です。
この追加装備も考え中ですが目立つところに増設したくはありません。
グローブボックス内に蓋つきで隠せるようにしようかと思案中です。
ロータスヨーロッパのワイパースイッチについて
ロータスヨーロッパの独特なスイッチといえばワイパースイッチです。
すごく硬いけど、壊さない様にひねるとワイパーが動く。
推すと水鉄砲式で押しただけウォッシャー液が出る。
はじめは、どうやってワイパー動かすかすらわかりませんでした。
ああ、スイッチひねるのね♪
・・わかったのはいいけど、
さらに間欠ワイパー機能がないので頻繁に動かす必要があります。
とりあえず、後付けの間欠ワイパーキットを入れました。
一応、もともとのスイッチも生かしてあります。
※取り付けに際して多少加工したのでそのうち記事にします。

この真ん中の丸いノブがそのワイパースイッチだ!
このワイパースイッチ自体をプッシュすることでウォッシャー液を噴出する水鉄砲方式を採用しています。
作りが凝っているくせに使いづらいです。
しかも壊れるとパーツがないです。
あっても猛烈に高いので手が出ません。
ロータスヨーロッパのスイッチ自体はあれもこれも壊れそうです。
単純なんですが作りがかなりいい加減というか、塩加減が濃いしょっぱい作りになっています。
壊れて高額の出費は嫌なので、ウォッシャー液の噴射スイッチは電動に作り変えました。
これで雨が降っても大丈夫ですが基本的に雨では乗りません。
※ワイパーの間欠ボリュームスイッチとウォッシャー液のスイッチは並べてセンターコンソールに増設しています。

右端の上がワイパースイッチ、下がウォッシャースイッチ。
ちなみに・・
ウォッシャー液はビニール袋に入って前側のトランク部についています。
※軽トラDAIHATU HIJETと同じ方式です。
ウォッシャー液用の後付けタンクはすでに買ってあります。
どこにどうやって設置したらいいのか未だに悩んでいます。
※面倒くさいので、そのうち本気でやります
実はウォッシャー液が元気よく噴き出ても、
ワイパーの拭きとり能力は異常に悪いです。
自分で噴射したウォッシャー液すらまともにふき取りません(笑)
※ワイパーはウォッシャー液をただ擦り付けてるだけの車検用と思った方がいいようです。
ロータスヨーロッパのトリップメーターについて
スピードメーターに内蔵されているトリップメーター(距離計)は普通はメーター自体についてるもんです。
ロータスヨーロッパの場合、ダッシュボードに地味についています。
長いワイヤで手前に引き回されているツマミを回転させてリセットします。
※わかるか、こんなもん(ほとんどバイクだわ)

こんなトリップメーターのリセット、普通わからんよ
あまりに後付け感が強烈で・・
まさかこれじゃねえよな?
と思ったらコレでした(泣)
知らなきゃトリップメーターのリセットできませんよ。
ロータスヨーロッパの純正メーターについて
純正とは言え、結構たくさんのメーターが付いています。
※アナログメーター好きにはたまりません♪
アナログメーターは、デジタルより情報量は少ないけれど雰囲気はあっていい感じです。
最近のデジタルメーターって情報量が多すぎです。
※デジタルメーターの液晶って20年くらい持つのかね?
がついています。

いいんですよ、動いていれば。正確さなんて求めるのは無駄です。
いずれも正確な値を指しているとはいいがたいです。
とくに油圧計があてになりません♪
でも、旧車のメーターなんてみんなそんなもんです。
メータなんて動いてりゃいいです。
いつもと大きく違う値を指してたら焦りますが正確な値なんて一切期待していません。
スピードメーターは針がぐわんぐわんと大きく動くので壊れているかもしれません♪
スピード&タコメーターが配置されているボックスは紙製か?
と思うくらいのペラペラの素材です。
なんだか和紙というか海外の段ボールみたいな素材です。
よくわかりませんが裏側を触るとダンボールみたいな感触でものすごく安そうな素材です。
※そこまで軽くしたかったのか?と思いますが、火が付いたら速攻で燃えそうです。
グローブボックスも同じ素材で加工はしやすそうです。
※濡れたタオルとか入れたらふやけそうです。グローブボックスには蓋はありません。
ちなみに・・
ロータスヨーロッパSPには大きく二種類のボディが存在します。
左ハンドルの北米仕様
右ハンドルの本国仕様
※もっと細かく分かれますが別記事にまとめました。
米国などに向けた左ハンドルボディ(フェデラルボディと呼ばれています)は、
などが右ハンドルの本国仕様とは細かく違います。
お金持ちの米国向けなので少しでも豪華にしたしたかったんじゃないかと推測します。
※フェデラルボディには乗ったことないけどシンプルな本国仕様が好みです♪
ロータスヨーロッパはパワーウィンドウ付き
意外にもロータスヨーロッパにはパワーウィンドウが付いています。
パワーウィンドウのスイッチはセンターコンソールについています。
純正のパワーウィンドウスイッチはとんでもなく安っぽいんですよ・・
スイッチ自体がセンターコンソールにはめ込まれているだけです。
土台となるセンターコンソールのゆがみもあって固定したつもりでもすぐに浮いてきます(笑
あまりに安っぽいので、同じ位置にパワーウィンドウのスイッチがある現行FIAT500やアバルト595のスイッチでも加工して付けてやろうかと思います。
現行車種のスイッチつけると旧車の雰囲気ぶち壊しなので少し躊躇しています。
※それほど許せないレベルのちゃっちいスイッチなんですよ(泣)
ちなみに・・
純正ではパワーウィンドウの回路にヒューズは存在しません。
割り切ったいい作りです(泣
※ヒューズを回路に追加しましたけどね・・
スイッチの裏にはこれ以上ない単純なホームセンターで買える端子がついています。
左右で付いているハーネスの数が違うので??と思ったら。
電源は右側のスイッチにいったん供給されて、渡り線で左側のスイッチに供給されているという素敵な仕様です。
スイッチ類全般について
スイッチは全部トグルタイプに変更したいなぁと思うのですが面倒なのでやってません。
なんであんな安っぽいスイッチにしたんだか・・
あんまり安っぽいので作り変えたい・・とはいえ、そう簡単に作り変えられるものではありません。
スイッチ類はダッシュボードに埋め込まれているので流用できるパーツは限られています。
気に入ったスイッチがあれば、ダッシュボードやセンターコンソールへの設置方法を考えれば何とかなりそうです。
二段階にスイッチングできるライトやファンのデザインの浮かないスイッチなんてあんまりないんですが。
ちなみに・・
メーターやスイッチのついているダッシュボードパネルの裏側はひどいことになっています。
もうぐちゃぐちゃに配線がっ走っています。
本気で配線のセンスを疑うレベルです。
っていうか、
設計した奴ちょっと来い!
無理やり配線してる感が半端ないです。
FRPのボディは漏電して発火したら全焼コースです。
全焼は怖いので入手してからかなり時間をかけてダッシュボード裏の電装の点検と整理をやり直しました。
ロータスヨーロッパを入手したら一度は確認したほうがいいと思います。
ですが、
根性のない人は見ないほうがいいです。
おそらく、
工場出荷時からこんな状態で歴代のオーナーさんたちは無頓着だったのではないかと推測します。
※英国旧車の電系は例外なくひどいです。ワタクシは旧miniで思い知っていたので大抵のことでは驚きゃしませんが。
まとめ
ロータスヨーロッパのスイッチやメーターは結構適当で素人でも配線がわかるレベルです。
ただし、かなりいい加減だし仕上げは雑です。
旧車の電装が結構いい加減なのはロータスヨーロッパに限ったことではありません。
50年近く前の車の歴代オーナーが、いつどんなふうに整備してたのかわかりませんし。
※ワタクシも作業記録は残していますがプロから見たら「そりゃないぜ」っていう手法で整備してるかもしれません。
ワタクシ的にはまともに動くことが最優先です。
なるべく普段使いが可能であること!も重要です。
純正にこだわらず、細かく各部をアップデートしながら乗ることにします。
アップデートの際にちょっとした発見があったり、ヤバそうな個所への対策、対応も楽しいです。
何があっても太古の車なんだし「そういうもんだ」と割り切らないと長くは付き合えません。
たとえ、しょぼくても素人が直接いじれるおもちゃ車を持っていることが幸せです。
ちなみに・・
古い英国車の電装は全部ひどいと大昔にMG-Bのオーナーが言ってました。
その時は聞き流していましたが・・本当にひどいです。
だいぶ前に、
HONDAがROVERと提携したことがありました。
あまりの電装の酷さにホンダが怒って
旧miniの最終型だけちょっとマトモな電装になったという噂はたぶん本当です♪
現代なら全部クレームだと思います。
いいなあ、おおらかな時代っぽくて♪